今月の1冊
2019年10月08日
小倉 ヒラク『発酵文化人類学-微生物から見た社会のカタチ』
今年の春あたりから「ぬか漬け」にはまっている。
胡瓜に人参、茗荷に牛蒡、時にはピーマンからセロリまで。
どんな野菜もぬか床に寝かせると、美味しいぬか漬けへと変身する。おかげで、いろいろな野菜を楽しむことができている。
美味しさは言うまでもなく、私が毎日楽しみにしているのが「ぬか床のお世話」かもしれない。
朝、仕事に行く前の気ぜわしい時。夜、帰宅後の疲れ切っている時。時間を決めているわけではないけれども、毎日毎日、ぬか床をかき混ぜると、ぬか味噌の柔らかさとひんやりとした感触、そして独特な香りに、気持ちがほぐれホッとするから不思議だ。
最初は、家でぬか漬けを食べたいけれども、毎日ぬか床をかき混ぜるのは面倒だな~という気持ちもあり、かき混ぜなくともOKというぬか味噌を手に入れたことから始まったぬか漬けライフだが、次第に普通のぬかを混ぜたり、味に一工夫を加えたくて、昆布や唐辛子などを入れていくうちに、かき混ぜ“お世話”することが日課となっている。
ぬけ漬けの面白いところは、毎日味が微妙に違うこと。
もちろん野菜の違いや質はあるけれども、気温や“お世話”で変化するぬか床の発酵具合によって、味も変化していくのである。毎日、ぬか床が「生きている」ことを実感しながら味わうぬか漬けはより美味しさを感じる。
『発酵文化人類学』
発酵+文化人類学・・・?この不思議な組み合わせは何処からきているのだろう。
著者 小倉ヒラクさんは「発酵デザイナー」の肩書を持つ。
目に見えない微生物のナビゲーター、私たちの暮らしを支えてくれている発酵菌たちのエヴァンジェリスト(伝道師)として国内外あちこちを巡り、世界中の発酵文化を伝えることが発酵デザイナーの仕事、とある。
小倉さんの大学時代の専門は文化人類学。
化粧品会社でのデザイナーなど、デザインの仕事で多忙を極め体調を崩しはじめていたとき、かの発酵学者 小泉武夫先生に出会う機会があり、「お前ッ・・・さては免疫不全だな。味噌汁飲め!納豆と漬物食え!」と言われ、実行したのが発酵の道に惹かれたきっかけ。みるみる体調は良くなり、発酵に興味を持つようになるうちに、世界中あちこちの土地の文化を表出する“発酵”について調べることは、大学時代にバックパックをかついで世界中を旅しいろいろな文化を見て回ることに夢中だった文化人類学の研究に似ている、と気づいた瞬間、「発酵+文化人類学」の組み合わせが浮かんだそうだ。
大豆に麹菌がつくと味噌に、ブドウにイーストがつくとワインに、牛乳に乳酸菌がつくとヨーグルトに・・・と、発酵とは微生物が人間に役立つ働きをしてくれることであり、世界中いたるところに美味しい発酵文化が存在している。
ホモ・サピエンス(賢い人)に倣い、ホモ・ファーメンタム(ラテン語で“発酵するヒト”の意。小倉さんの造語)とも言えるほど、目に見えない微生物とコミュニケーションを取り文化を生み出しているのが、私たち人間なのである。
ここ数年の健康ブームの流れもあり、発酵食品は一段と注目を浴び、発酵産業は大きなマーケットになっている。いまや町おこしに発酵食品が一役買っている例もあるそうだ。そのなかにあって、パッケージやパンフレット、ウェブのデザインといったいわゆるデザイナーの枠を超えて、半分研究者、半分コミュニケーターとして、技術や文化を橋渡しするのが発酵デザイナーの役割である、と小倉さんは自らの仕事を位置付けている。
世の中には思いもよらないニーズがあり、そこに新たな仕事を見出すというイノベーションを興すことに感心してしまう。
発酵文化人類学とは
発酵を通して、人類の暮らしにまつわる文化や技術の謎を紐解く学問
と定義されている。
本書は、発酵文化について学術的に記載されているわけではない。
もちろん、発酵プロセスや発酵食品の製法についての解説はあるにせよ、発酵デザイナー小倉さんの1冊らしく、発酵と文化人類学から派生し、宗教やデザイン、アート、さらに遺伝学など、一見関係なさそうなさまざまなトピックスと発酵が結び付き、発酵文化の世界がデザインされているのである。
発酵文化を知るうえで、まず興味を持つのが、その多様性。
土地の数だけ発酵食品あり、とまで言われるほど、各地独自の発酵食品が存在し文化を形成している。
小倉さんが日本各地で出会った個性的な発酵食品を解説しながら、土地に伝承されてきた郷土食文化の奥深さを紐解くと、現代の科学の目で見ると奇想天外に見える発酵食品も、合理的にデザインされていることがわかるから面白い。
その代表例が「くさや」。
伊豆諸島 新島のものが紹介されているが、アジやトビウオなどの青魚をくさや液という発酵液に浸して干したものであり、火を通すと強烈な異臭を放つのだが、身はホロホロとして美味しいという有名な発酵珍味である。これは、江戸時代に生魚を日持ちさせるために塩漬けののち干物としていたものの、塩は税として取り立てられ制限されるため、塩漬けのつけ汁を捨てずにリサイクルし、継ぎ足し使っていたものが発酵してきたことがくさやのルーツだそうだ。
私も食べたことがあり、くさやを焼く臭気は家中に広がりいたたまれないが、勇気をもって口にすると美味しいという、まさに珍味である。
でも、なぜ、くさやが腐らないのか、むしろなぜ腐敗を防ぐのか、くさやの発酵作用には科学的にはわからないことがたくさんあるらしい。
実は、多くの発酵食品にはいまだに科学的に解明できていないことが山ほどあり、何十年研究しても謎が解明されない理由は大きく2つあることを小倉さんは示している。
- 分離できる菌とできない菌がある
- 複数の菌が連携して行う発酵作用が分析しづらい
分離できない理由の1つとして、その菌が単独では生きていけず、複数の菌が協同して何らかの発酵作用をし、「チームの働き」によって複雑な作用を起こしていることが、科学的解明の難しさでもあり、美味しさの秘密でもあると言える。
まさに発酵菌におけるチームプレーの美学!
私の大好きなぬか漬け、さらにキムチなども関与する微生物の種類が多いので、科学的な分析が追い付いていないそうである。
発酵とは、文化人類学者 レヴィ・ストロースが言うクリエイティビティは個人の才能から生み出されるものではない、という世界観に通じると小倉さんは語る。自然をつぶさに「観察し」、人間の世界と自然の世界をつなぐ関係性を「発見する」時に結果として神話や文化体系が生まれる。
発酵の発明とは、目に見えないミクロの自然と人間の世界をつなぐ関係性のデザインであり、発酵の背景を紐解くと、その土地に住む人たちが世界とどのように向き合ってきたのかがわかる、という指摘は実に興味深い。
この夏、小倉さんは、情報技術の研究者であり社会とテクノロジーのより良い関係性のあり方を学際的に探究し、発酵に関する考察でも有名なドミニク・チェンさんらとともに開発した「ヌカボット Nukabot」を公開し、国内外の展示会で話題を呼んでいる。
ヌカボットには、発酵具合や菌の活動を測定するセンサーが内蔵されており、「そろそろかき混ぜたら?」や「いま食べごろ」などぬか床やぬか漬けの状態を知らせてくれるぬか漬けロボットだそうだ。
それは、放置してしまったりと、ぬか床をうまく育てることのできなかったドミニクさんの経験から生まれたもの。でも、すべて自動化するのではなく、ぬか床をかき混ぜるのは「人の手」であることにはこだわっている。
ぬか漬けは漬けた人の手の菌も必要であり、人の手が入らないとぬか漬けでなくなる可能性がある、という発酵の不思議からきているもの。そう、人の手の菌も発酵のチームプレーの大切な一員なのだ。
すべて解明できていないからこそ面白い。
理屈ではわからない味や美味しさを発見できるから面白い。
手をかけすぎてもいけないが、人の手で毎日お世話することで変化していくのが面白い。
これから季節も変わり、私のぬか床はどう変化していくのだろう。
ぼんやりと、でも、明日に向かって着々と思いをめぐらす。
この絶妙なるバランス、ゆらぎこそが、ぬか床をお世話する楽しみなのかもしれない。
発酵とは、実に奥深い。
(保谷範子)
登録

オススメ! 春のagora講座

4月20日(土)開講・全6回
真山 仁さんと語らう【小説の舞台裏と現代日本の課題】
『ハゲタカ』シリーズ著者の真山仁さんと、現代日本の金融、財政問題について多面的に考え、考えを磨きます。

オススメ! 春のagora講座
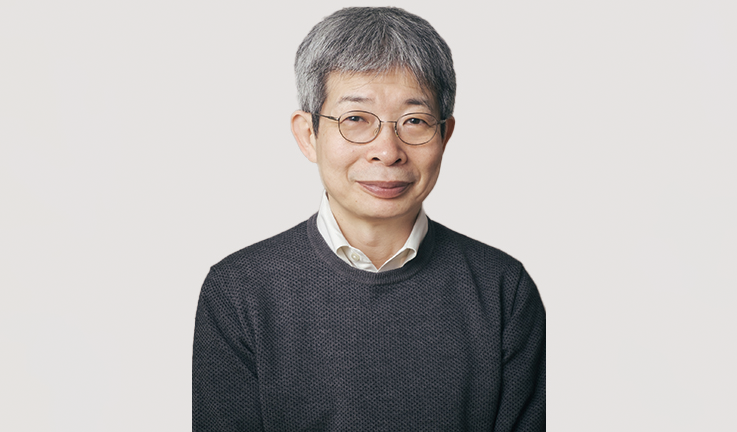
4月21日(日)開講・3日間全6回
平田オリザさんと創る【表現力を磨く演劇ワークショップ】
国際化時代のコミュニケーション能力とは、そのツールとしてなぜ演劇や芸術が重要なのかを考え体験します。

オススメ! 春のagora講座

5月11日(土)開講・全6回
小泉悠さんと読み解く【世界の軍事戦略】
世界の軍事戦略を、最先端のサイバー・情報戦などを含め多面的に取り上げ、これからの安全保障を読み解きます。
登録





