ファカルティズ・コラム
2025年07月04日
「顧客を巻き込む」マーケティング戦略
ビジネス、特にマーケティングに携わる方なら「コミュニティマーケティング」「ファンマーケティング」「アンバサダーマーケティング」という言葉はご存じでしょう。
しかし、この3つのマーケティングは何が違うのか、そう感じている方もいらっしゃるはず。
これらの手法は、どれも「顧客との絆を深める」という点では共通していますが、そのアプローチや目指すゴールには明確な違いがあります。
そして、この3つのマーケティング手法を巧みに操り、成功している企業がワークマンです。
今回は、ワークマンの事例を中心に、それぞれのマーケティング手法がどう機能しているのかを解説していきます。
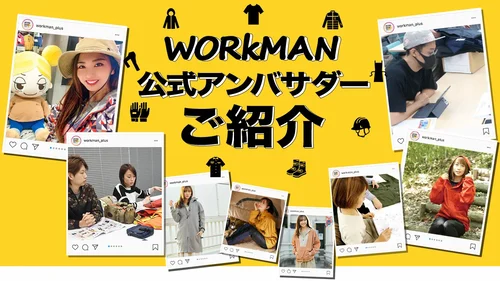
1. コミュニティ・マーケティング:顧客が集い、語り合う「居場所」を作る
コミュニティ・マーケティングとは、顧客同士、あるいは顧客と企業が交流できる「コミュニティ」という居場所を形成し、その中で情報交換や体験共有を促進する手法です。目的は、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化、そして結果的な新規顧客の獲得です。
ワークマンは、積極的に公式なコミュニティサイトを運営しているわけではありません。しかし、その代わりにSNSが非常に活発なコミュニティの場となっています。
「#ワークマン女子」「#ワークマンプラス」**といったハッシュタグを検索してみてください。そこには、ワークマンのアイテムを使ったコーディネート写真、機能性レビュー、購入品紹介などがずらりと並んでいます。
ユーザー同士が「これ買いました!」「この使い方いいですよ!」と情報を交換し合い、互いの投稿に「いいね」やコメントを付けていということは、まさに顧客自身が作り出す巨大な情報交換コミュニティがそこにあると言えます。
企業側が「場」を提供するだけでなく、ユーザーが自発的に集まり、情報が循環しているのがワークマンの上手いところ。この活発な交流が、新たな顧客の興味を引きつけ、「私もワークマンデビューしてみようかな?」という購買行動に繋がっています。
2. ファンマーケティング:「大好き!」な気持ちを育てる仕掛け
次のファンマーケティングですが、これは、自社の商品やサービス、ブランドに強い愛着を持つ「ファン」を育成し、そのファンとの関係性を深めることで、中長期的な売上向上とブランド価値の向上を目指す手法です。顧客を単なる「購入者」ではなく、ブランドを愛し、応援してくれる「ファン」として大切に育てるイメージです。
ワークマンは、従来の作業着のイメージを刷新し、ファッション性や機能性を兼ね備えた製品で、幅広い層から支持を得ています。高品質でデザイン性の高いウェアが低価格で手に入る。この「価格以上の価値」を提供することで、顧客は「ワークマン、すごい!」と感じ、強い愛着を抱くようになります。
これは一度ハマったら抜け出せない「沼」のようなもので、「#ワークマン巡り」というハッシュタグが生まれたように、多くのファンは新作が出るたびに店舗を訪れ、SNSでその情報を共有します。これは、スターバックスの新作フラペチーノを求めて行列ができたり、限定グッズを買いに走ったりするファン心理と共通しています。
そしてこれは後述するアンバサダーマーケティングにも繋がります。SNSの顧客の声を積極的に聞き入れ、製品改善や新商品開発に活かす姿勢は、ファンに「自分たちの意見が届いている」という喜びを与え、さらにブランドへの愛着を深めます。
スターバックスコーヒーが「Starbucks Rewards」で顧客の購買行動を促し、限定特典でファンを育成しているように、ワークマンもまた、その製品力と顧客への寄り添いを通じて、熱狂的なファンを増やし続けています。
3. アンバサダーマーケティング:信頼できる「声」で輪を広げる
そして、今回最も注目したいのが、アンバサダーマーケティングです。
これは、自社の商品やサービスを深く理解し、熱心に支持してくれる「アンバサダー(宣伝大使)」を任命し、彼らが自らの体験に基づいたリアルな情報を発信することで、新規顧客の獲得やブランドの信頼性向上を目指す手法です。
ワークマンがアンバサダーマーケティングにおいて他社と一線を画しているのは、その「本物」へのこだわりと「共創」の精神です。
ワークマンのアンバサダーは、単にフォロワー数が多いインフルエンサーではありません。彼らは、キャンプ、バイク、釣り、ゴルフなど、それぞれの分野で実際にワークマン製品を愛用し、その機能性や品質を深く理解している「現場のプロ」であり、「ガチ勢」です。
例えば、カリスマキャンパーのサリーさん。彼女が自身のブログやSNSでワークマンの「綿かぶりヤッケ」を焚き火ウェアとして紹介したことで、この製品はキャンパーの間で大ヒットしました。
他には、バイクジャーナリスト、釣り愛好家、猟師など、各分野の専門家がアンバサダーとして活動しています。彼らの発信は、金銭目的の宣伝ではなく、心からの「好き」と「体験」に基づいているため、消費者に絶大な信頼感を与えます。
驚くべきことに、ワークマンの公式アンバサダーの多くは、金銭的な報酬を受け取っていません。交通費や試供品の提供はあれど、基本的には無償で活動しています。
では、なぜ彼らはそこまで熱心に活動するのでしょうか? それは、「製品開発に直接関われる」という、ファンにとってこれ以上ないほどの「プライスレスな体験」があるからです。
サリーさんと共同開発した「フルジップコットンパーカー」のように、アンバサダーの意見やニーズが、実際に新商品や既存製品の改良に反映されるのです。自分が「こうだったらいいのに」と思ったことが形になる。これは、単なる宣伝では得られない大きな喜びとやりがいです。
アンバサダーは、ワークマンというブランドを「自分たちのブランド」として捉え、共に成長させている感覚を抱いているのでしょう。
アンバサダーが自身のSNSやブログで、製品のリアルな使用感や活用方法を発信することで、それが質の高いUGC(ユーザー生成コンテンツ)として拡散されます。彼らの発信は、「専門家が実際に使って太鼓判を押している」という信頼性があります。
この信頼感が、新たな顧客層(特に女性やアウトドア層)がワークマン製品に興味を持ち、購買へと踏み出す強力な後押しとなっています。
ワークマンは、テレビCMから撤退し、その分の費用をアンバサダーマーケティングなど「人」を介したプロモーションに投資しています。これにより、莫大な広告費をかけずに、これほどのブランドイメージ変革と顧客層拡大を成し遂げているのは、まさにアンバサダーマーケティングの理想的な成功モデルと言えるでしょう。
ワークマンから学ぶ「顧客との新しい関係性」、いかがでしたでしょうか?
コミュニティ・マーケティングは、顧客同士の交流を促し、情報が自然に循環する「場」を作る。ファンマーケティングは、顧客の「大好き!」な気持ちを育て、ブランドへの深い愛着を育む。アンバサダーマーケティングは、信頼できる「本物のファン」に語ってもらい、その熱量を新たな顧客に伝播させる。
ワークマンは、これらの手法を単独で使うのではなく、有機的に連携させている点がポイントです。コミュニティから熱心なファンが生まれ、その中からアンバサダーが誕生し、さらに彼らの発信がコミュニティを活性化させる…という好循環を生み出しています。
「広告で一方的に語りかける」時代から、「顧客と共にブランドを育て、共に歩む」時代へ。
ワークマンの戦略は、まさにこれからのマーケティングの姿を示していると言えるでしょう。

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)
慶應MCCシニアコンサルタント
慶應MCC担当プログラム
ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎
デザイン思考のマーケティング
フレームワーク思考
イノベーション思考
理解と共感を生む説明力
大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタ®」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。
また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。
主な著書
『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社
『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年
『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社
『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年
『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年
『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年
『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版
登録
登録








