ファカルティズ・コラム
2007年12月07日
正しく“あいづち”打ってますか?
言うまでもなく、コミュニケーションにおいて“あいづち”は重要です。
相手と対話する際、身じろぎもせずに黙っていては、相手は「ちゃんと聞いているのかな?」と不安になってしまうからです。
ですから相手の話すペースに合わせて、適宜「はい」や「うん」、時には「ほお」や「なるほど」「それで?」といった形で、言葉であいづちを打つ必要があります。
この時、言葉以外の非言語情報、つまり声の大きさや調子・抑揚(聴覚情報)、表情の変化や身振り手振り(視覚情報)も加えてあいづちに変化をつければ、相手はより気持ちよく話してくれるようになります。
「ああ、ちゃんと聞いてくれているな」「自分の話に共感してくれているな」と感じるからです。
たとえば、淡々と言う「なるほど」と、大きく目を見開いて声のトーンも上げた「なるほどー!」では、明らかに共感の度合いが違って感じられるはずです。
あいづちとは、単にコミュニケーションの常識でなく、相手(同僚・顧客・友人・恋人)から、信頼感・親近感・安心感を勝ち取るツールなのです。
そしてあいづちの基本となるボディアクションに、“うなずき”があります。
このあいづちにおける“うなずき”、実はいくつかのバリエーションがあります。
(1)「はい」や「うん」と合わせて普通にコクリとやるうなずき。
(2)大きく深くコックリ(居眠りではありません)とやるうなずき。
(3)小さく何度もコクコクとやるうなずき。
(2)は深い共感や同意を表現していますから、相手はさらにノってきます。
(3)は、「それでそれで?」と良い意味で急かすことになり、相手は「もっと話を聞きたいのだな」と思ってくれます。
どちらもシチュエーションによっては、コミュニケーションの活性化に大きな効果が期待できる、あいづちのテクニックと言えます。
しかし、うなずきのバリエーションで、ひとつだけやってはいけないものがあります。
それは「あごを高く上げてからうなずく」というものです。
なぜやってはいけないかと言うと、「偉そうに見える」、つまり相手は自分が軽視されているように感じてしまうからです。
「君の話は先刻ご承知だが、聞いてあげるよ」、という印象を与えてしまうのですね。
ではなぜ偉そうに見えるかと言うと、あごが上がりすぎると必然的に「上から目線」になるからではないかと。
なんとなく、「見下している」ように見えてしまうわけです。
こちらにそんな意識がさらさら無くても、それをどう受け取るかは、相手が決めることです。
せっかくのあいづちが誤解されては、もったいないと言うほかありません。
ということで本日のスキルアップ標語です。
「うなずきは、バックスイング小さめに」
登録

人気の夕学講演紹介
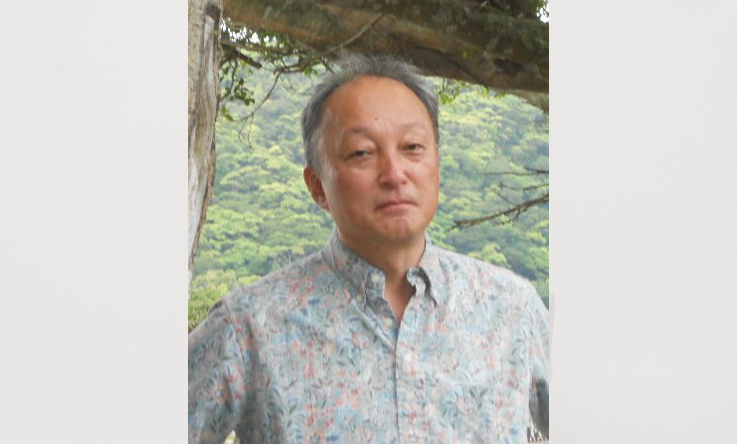
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
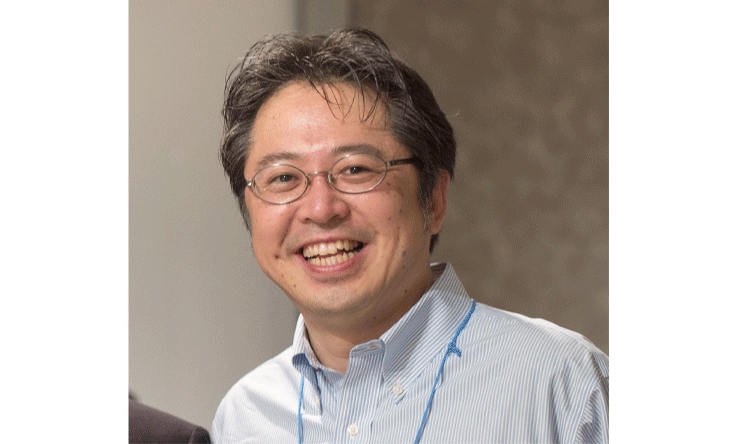
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




