ピックアップレポート
2025年09月09日
井手 英策著『令和ファシズム論——極端へと逃走するこの国で』
私だけが不安なのだろうか?
経済は勢いをなくし、街は外国人であふれ、発展途上国のようになりはじめた日本経済。思慮を欠き、暴言や不道徳が幅をきかせる政治。財政規律のゆるみと横行するバラマキ。世代内、世代間で共有されない価値観。多くの人がふつうにくらしている。鋭い痛みがあるわけではない。でも、まるで少しずつやせおとろえ、衰弱死をむかえるような、そんな言いしれぬ不安が、私にまとわりついてはなれない。
私は、この不安の淵源にせまろうと考え、ある大きなテーマを設定した。
それは、ずばり「ファシズム」だ。
あらかじめ断っておくと、私は、ファシズムの再来をうったえて、みなさんをおどかすつもりはない。ファシズムという暗黒の時代のできごとを知り、当時の空気を感じとることで、令和における日本社会の不安の病巣を知る手がかりをえたいのだ。
財政史というメスで社会を解剖する
社会を解剖し、不安の病根にたどりつくためには「メス」がいる。私がもちいるのは、財政史という名のメスである。
人類は、欲望をみたすための「市場経済」と同時に、連帯と共助のシステムである「財政」をつくりだした。財政があるから、経済活動が生みだす不平等が修正され、社会の分裂が食いとめられる。生きていく、くらしていくための「必要(ニーズ)」をみたすために、政治の場で対象(なにを)と方法(どのように)を話しあう。税をあつめ、経済的な資源を配りなおし、社会に秩序をもたらす。これが財政の目的、いや本質である。
財政現象は、経済的であり、社会的であり、政治的である。だから、財政の歴史にまなべば、ある時代がどんな経済状況におかれ、人びとがどんな価値観をもち、なぜ対立し、和解したのかを知ることができる。
財政とは社会をうつしだす鏡である。ここでは経済史でも、政治史でも、社会史でもなく、財政史という一風かわった、そして多くの研究者が使いこなせなかったメスをもちいて、日本社会の病根をえぐりだしていく。
「ポピュリズム」で終わらせない
財政は、支出と収入からできている。その両者をきめるプロセスでは、参加者たちの利害関係や理想とする社会観のちがいから、はげしい対立が生まれる。好き、きらい、ときには嫉妬や憎しみとともに財政はかたちづくられる。
この闘争劇に登場する人びとの立場をあらわすのが、「左派」「右派」 という基準である。
人間の理性や知性の力を信じ、あるべき未来図にしたがって社会をかえていけば、世の中はきっとよくなる、と考える人たちがいる。彼らを左派とよぶ。反対に、理性や知性の限界を知り、歴史的に根拠をもち、権威あるものにしたがって秩序を保とうとする人たちがいる。右派である。前者は、革新派、リベラル派、後者は、保守派とかさねられながら、政治や政策をかたるときの思想的な配置、大枠はしめされる。
いま私たちの目のまえで、この枠組みが音をたててくずれようとしている。
私たちが、日常の政治で目にしているのは、左右の「違い」と同時に、「接点」である。遠くてちかいふたつの極。 思想的な垣根と枠組みは〈溶解〉しはじめ、理念よりも大衆の声をおもんじる態度がひろがり、左右で政治を対立的にとらえる見かたの限界もあらわになりつつある。
こうした時代状況は、しばしば「ポピュリズム」と表現される。だが、歴史学者エンツォ・トラヴェルソが喝破したように、ポピュリズムという概念は、定義があいまいであり、自己の立場を正当化したい人たちによる、既存の秩序に抵抗する人たちへの烙印、レッテルでしかない。
私は、いまの日本の政治や財政にポピュリズムというレッテルを貼るつもりはない。なんとなくファシズムと同一視しながら、ポピュリストに倫理的な批判をくわえる気もない。
私が関心をもっているのは、ポピュリズムであれ、ファシズムであれ、はじめは、民主主義の枠内でおこなわれたはずの運動が、どのように民主主義を破壊することになったのか、なりうるのか、という問題である。
そもそも、左右という思想の線引きが説明力をなくし、ポピュリズムのようなうごきがつよまる時代とはどんな時代だろう。
それは、「当然」が機能しなくなる時代である。成長してあたりまえだった経済は、長期停滞にあえぎ、いくら政策を動員しても、十分な成果がえられなくなる。対話と調整の場であった政治は、対立や非難、論破の空気で支配されるようになる。善悪や近世以来の道徳といった、社会的価値までもが再考をせまられる。常識が常識でなくなる。それまでの思想は説明力をうしなう。だから、あらたな思想、あらたな秩序をもとめる政治闘争がはじまる。
ところが、突如としてすべてを刷新しうる思想が生まれるわけではない。だからこそ、政治的に居場所を見つけられない人たちにねらいをさだめ、具体的な理念や意味内容をもたないにもかかわらず、 最大公約数的にだれもが同意できそうな、所得を増やす、国をまもる、ムダをなくすといった言葉が政治の世界をとびかうようになる。権威に人民を対峙させる。これがポピュリズムの政治戦術である。
こうして、政策をめぐる思想的な線引きは意味をなくしていく。財政は社会をうつしだす鏡だとのべたが、常識が常識でなくなり、思想の垣根が溶けだしていけば、当然、財政のありようや、その前提にある規律もゆらがずにはおかない。
経済が不安定になれば、人びとは、生活や将来への不安から自己の生活防衛にはしり、他者の困難への無関心をつよめていく。手取りをへらすように見える税はきらわれ、徹底した批判にさらされる。経済成長へのこたえが見つからない政治家は、国民の失望をおそれ、票集めに必死になり、不道徳の象徴であった借金をためらうことなく実行する。
もうおわかりだろう。財政赤字は、たんなる収支の過不足ではない。動揺する社会のさけびであり、悲痛なさけびの「結晶」こそが、巨額の政府債務なのである。
日本社会は右傾化したのか
思想の垣根が溶けだす時代。そのなかでも、私がとくに関心をもったのは、小泉純一郎内閣の誕生以来、学会、論壇、マスメディアのあちこちでおこりはじめた、日本社会の「右傾化」を心配する声だった。
均衡財政や福祉の抑制をもって定義するなら、小泉純一郎内閣の政策運営は、あきらかに経済的に保守化していた。私は、恩師と二〇〇六年に編んだ本のなかで、新自由主義的な経済政策を「民主主義を壟断する邪な試み」と非難し、政府が「財政破綻」という「恫喝」を口実としている状況をきびしく批判し、再分配の強化をもとめた。私たちの懸念のとおり、経済的保守化は格差社会をうみ、歴史的な政権交代をもたらした。だが、それもつかのま権力は、その三年後に保守政党へともどっていった。
第二次安倍晋三内閣では、政治的な保守化が進んだ。道徳教育の科目化、集団的自衛権の行使容認、共謀罪の法制化など、目まぐるしいスピードで「改革」はすすんだ。同内閣の首相や閣僚たちが、ナショナリスト団体である日本会議の役員をつとめている、神道政治連盟に国会議員の約四割が参加している、と報じられたとき、私は、政治の右傾化を目のあたりにした気がした。
同時におきていた左傾化
本当に右傾化が進んでいるのか、それがどの領域で進んでいるのかについて、はっきりと結論がでているわけではない。それどころか、おちついて現実を見なおしてみると、右傾化をおもわせる変化と反対の変化も同時におきている。
最近の政治を見てみよう。 岸田文雄内閣で制定されたのは、「LGBT理解増進法」だった。当事者たちからは、保守的な条文に批判の声が投げかけられたが、かつての自民党であれば想像もできないリベラルな法案が国会を通過した。右派として論陣をはる百田尚樹が、同法案の成立は自民党の左傾化だ、自民党をゆるさない、となげき、日本保守党の結成を表明するにいたったのにも、それなりに理由があった。
日本の企業や自治体、教育の現場をもまきこんで広がりを見せているSDGsを右傾化とみなす人はいないだろう。人や国の不平等をなくそう、気候変動に具体的な対策を、ジェンダー平等を実現しよう……いずれの政策目標も、左派がこれまでうったえてきた政策のまとまりであることは、だれの目にもあきらかである。
現実には、右むきのうごきと反対のうごきが同時におきている。右とみなされてきた人たちが左の政策を先取りし、左とみなされてきた人たちが右よりの政策に理解をしめしている。左右における政策志向の一体化。この現実を正面からうけとめるのであれば、日本社会の右傾化より、思想的な垣根の溶解現象の意味こそが問わなければならないはずである。
肯定的な未来に居場所を
左傾化、右傾化のどちらかいっぽうが世の中をおかしくしたのではなく、さまざまな思惑が交錯することで、両者が共振・共鳴し、ファシズムとよばれるような状況がうみだされた、というのが、私の見立てである。
日本を例にとると、日露戦争のあと、社会主義思想がひろがり、大正デモクラシーの時代がおとずれた。だが、民主主義のふかまりは、軍人や官僚たちのルサンチマン、左派への憎悪をかきたて、社会主義と対峙する国家主義運動をおびきよせた。その後、世界恐慌や満州事変をきっかけに急速な右傾化、保守化がすすんだが、左派はこれを否定するのではなく、むしろ右派との政治的距離をつめることで状況を利用しようとした。
歴史がこのような左右の奇妙な反発と親和で成りたっているからこそ、日本社会が左傾化・右傾化しているのか/していないのかではなく、現代において思想の線引きが説明力をなくしていることが、どのように「悪しき極端の束」につながりうるのかを考えなければならないのである。
エクストリーミズムは、左でも、右でもないから、オールドメディアの批判の対象になりにくい。むしろ、彼らは、極端な思想と思想とを、あたかも自然な選択肢であるかのごとく対比する。私たちは、すこしずつ極端な状況になれ、混沌へとみちびかれていく。
エクストリーミズムは、希望にみちた未来像をしめさない。彼らが語るのは、みじめな現実であり、大胆だが、急場しのぎでしかない解決方法である。だが、それらは、パッチワーク的なものだ。つぎはぎされた社会を待つ未来は、いったい、どのようなものなのだろう。
くらく、茫漠とした未来から逆算すれば、現状もまた停滞的で、ぼんやりとしたものになる。いまをどう愉しみ、どうおりあいをつけるのかが社会の関心事となる。不安から逆算される現状は、未来への恐怖と自己防衛をもたらす。そこに肯定的な未来の居場所はない。あるのは、あきらめという名の現状肯定である。
私はこれから、現代の社会状況を理解し、評価するための基準を手にいれるために、 「ファシズム前夜」の日本財政の歴史を追跡し、それをドイツの経験と対比していく。繰りかえすが、都合のよい事実をきりばりして、ファシズムの到来をさけぶつもりはない。いまの日本でおきつつあることが、かつての悲惨な歴史体験と、どこが重なり、どこがズレているのかを評価する〈基準〉を手に入れ、現代の不安の輪郭を描くことが目標である。
日本社会をおおう、このぼんやりとした不安の正体はなにか。このおおきな問いを意識しつつ、財政を専門とする私の目から見た、社会不安の解剖学をしめしてみたい。
『令和ファシズム論——極端へと逃走するこの国で』(筑摩書房 2025年8月)を著者と出版社の許可を得て抜粋・編集・追記しました。無断転載を禁じます。
※より原文に近い内容はWEBちくま「冒頭ためしよみ緊急公開」よりご覧いただけます。
慶應MCCでは、2025年10月11日(土)より上記書籍をテーマとしたagora講座「井手英策さんと語り合う『令和ファシズム論』」(全6回)を開講します。
―日本社会に漂う不安の淵源について深く考察したい方
―忍び寄るファシズムを歴史に照らして分析し、今を俯瞰的視点から理解したい方
―井手先生の最新の研究に触れ、これからの日本社会のあるべき姿を考えたい方
にお勧めの講座です。井手先生とともに日本について熱く語り合いませんか。
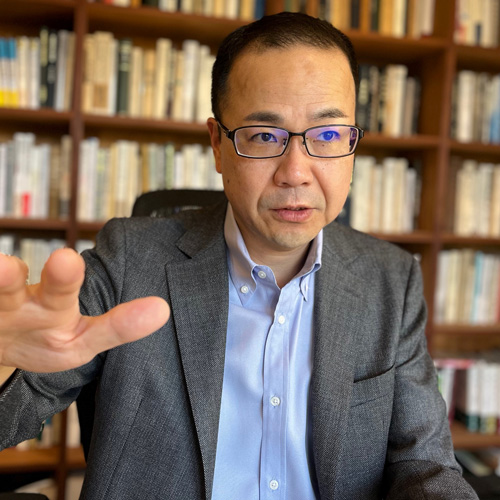
井手 英策(いで・えいさく)
慶應義塾大学経済学部 教授、かながわ福祉大学校 校長
1972年福岡県生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。日本銀行金融研究所に勤務。その後、東北学院大学、横浜国立大学などを経て、現職。専門は財政社会学、産業社会学。総務省、全国知事会、全国市長会、日本医師会、連合総研等の各種委員のほか、小田原市生活保護行政のあり方検討会座長、朝日新聞論壇委員、毎日新聞時論フォーラム委員なども歴任。2015年大佛次郎論壇賞、2016年慶應義塾賞受賞。
登録
登録









