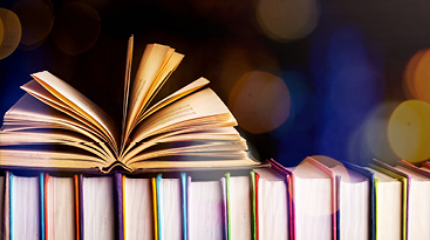MCC MAGAZINE
MCC MAGAZINE UPDATE
平井 孝志著『頭の中のぐちゃぐちゃがスッキリする思考の「型」』
売上アップの方法、新商品の売り方、プレゼンでクライアントに刺さる内容……。人に聞いてもいま一つわからない、と悶々とすることはありませんか?
- 2026年2月9日
- ピックアップレポート
菊澤 研宗著『組織の不条理を超えて 不敗の名将・今村均に学ぶダイナミック・ケイパビリティ論』
1980年代の半ばごろ、私は防衛大学校で経営学の教官をしていた。当時、防衛大では経営学の評判が悪く、民間企業が金もうけをするための学問だととらえられていた。そして学生たちが経済活動へ関心を持ち、任官を拒否して企業に就職してしまう原因だとみなされていた。
- 2026年2月9日
- ピックアップレポート
西尾 維新著『掟上今日子の備忘録』
「もし明日記憶がリセットされるなら、今日をどのように生きようか?」——探偵モノの推理小説でありながら、このような人生への問いを投げかけてくれる作品でもあると思う。
- 2026年2月9日
- 今月の1冊
藤井一至氏講演「すべては「土」から始まる」
藤井七冠。その噂は、かねがね耳にしていた。
SOTAではなく、KAZUMICHIのほう。将棋ではなく、土の人のほう。
- 2026年2月3日
- 夕学レポート
松本 紹圭氏講演「グッド・アンセスター~私たちはよき祖先になれるか~」
子孫への責任を問う「グッド・アンセスター」というテーマを聞いた時、正直なところ、人はそこまで遠い未来に目を向けることができるものだろうか、と疑問を持った。そもそも「よき祖先」とはどんな祖先なのだろう?
- 2026年1月28日
- 夕学レポート
美容家電戦国時代を走る4社の正体
先日の朝、鏡を見たらひどい寝癖が!
ドライヤーで直そうと思って洗面台の扉を開けたら、お目当てのドライヤーの代わりに電源コードの付いた見慣れぬロゴのブラシがありました。
「SALONIA(サロニア)?」
いわゆるヒートブラシと呼ばれる美容家電のひとつでした。無事それで寝癖は直せたのですが、ちょっと気になって調べてみました。
- 2026年1月22日
平藤 喜久子著『宗教のきほん 人間にとって神話とは何か』
最初に、一枚の絵を見ていただきたいと思います。フランスの画家ポール・ゴーギャンが描いた「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」(一八九七〜九八年)という作品です。
- 2026年1月13日
- ピックアップレポート
城取 一成(慶應MCCゼネラル・マネジャー)
『先祖の話』
柳田国男(著) 角川ソフィア文庫(2013年)
- 2026年1月13日
- 私をつくった一冊
岡根谷 実里著『世界の台所探検 料理から暮らしと社会がみえる』
台所探検家という肩書を聞いたことがあるでしょうか。
著者 岡根谷実里さんは、自らをそう名乗り、世界各地の家庭の台所を訪ね歩いています。料理を学ぶためでも、レシピを集めるためでもありません。
- 2026年1月13日
- 今月の1冊
2026年のキーワード:AIエージェント
明けましておめでとうございます!
2026年の幕開け、あなたは今年がどのような年になると予想しますか?
私はやはり、「イノベーション」の視点で今年を考えています。
昨年は、テクノロジー業界で「AIエージェント元年」という言葉が飛び交った1年でした。多くの企業がその可能性を模索し、実験を繰り返してきましたが、今年2026年は、それが実験室を飛び出し、私たちのビジネスや生活のあらゆる場面で「当たり前」のインフラとして活用される実働の年になると予想されています。
今年最初のエントリーは、今さら聞けない「生成AIとAIエージェントの違い」から、私たちの未来がどう変わるのかまでを、できるだけわかりやすくまとめてみたいと思います。
- 2026年1月6日