夕学レポート
2017年04月03日
第21回 7/14(金)壬生 篤さん
 7/14(金)は作家・編集者 壬生篤さんのご登壇です。
7/14(金)は作家・編集者 壬生篤さんのご登壇です。
寿司に天ぷら、鰻・・・など、現代でも和食として食べられている料理の数々は、江戸時代にその原形ができあがっていたというのは広く知られているところです。
江戸は二百年前からロンドン、パリ以上の人口を抱える世界最大級の都市であり、絵画や文学などの水準の高さに加え、人々は豊かな食文化を楽しんでいたと、壬生さんはおっしゃいます。
壬生さんは、江戸から明治の文化に精通し、特に食文化については、豊富な知識とともに数々の著書もお書きになっています。
原作を務めた漫画『文豪の食彩』はテレビドラマ化もされ、日本を代表する文豪達が何を食していたのか、日本の豊かな食文化、それらは現代につながっていることに興味深くご覧になった方も多いことでしょう。
今回は、鎖国によって近代化が遅れている・・・という誤った私たちの認識を覆してくれるような、世界にも誇る高い文化水準の”江戸時代の食”をテーマにお話しいただきます。
食べているものをみればその人がわかる・・・と言われます。
いまも昔も、食文化からは、その時代を生きている人の息づかいや躍動感が感じられるのでしょう。
当日のお話では、江戸時代にタイムスリップするような、江戸の生活を垣間見ることに今からワクワクしています。(保谷)
・壬生 篤
・作家・編集者
・演題:「探索!”江戸の食”~それが今、教えてくれるもの~」
プロフィールはこちらです
登録

人気の夕学講演紹介
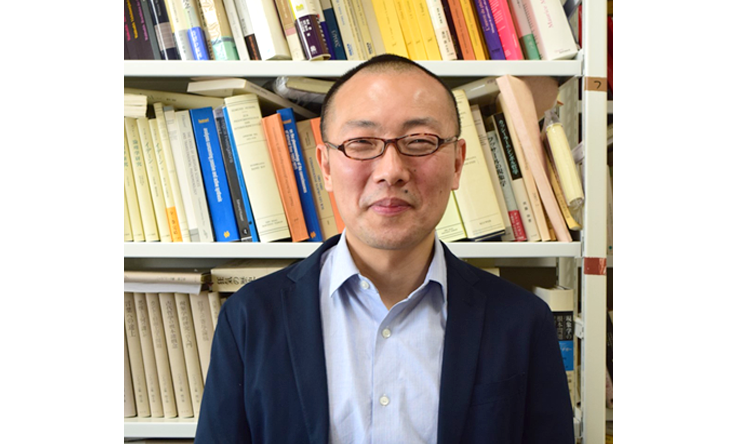
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
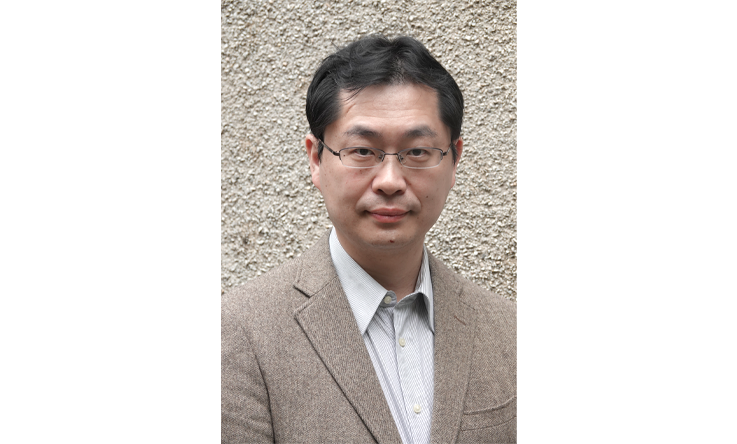
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




