ファカルティズ・コラム
2009年09月11日
“市場シェア”の考察(1)
事業戦略系のワークショップでは、しばしばこう質問されます。
「市場シェアはどのくらいを目指すべきなのでしょうか?」
これ、難しい質問です。
一応目安としては、コロンビア大学の数学者B.O.クープマンの提唱した「クープマン目標値」があるものの、これが全ての業界で通用するわけではありません。
(この「クープマン目標値」については、次回解説します)
しかしその前に考えてほしいことがあります。
それが、「市場シェアがどのような意味を持つのか?」です。
自社のシェアを「知ること」にどのような意味があるのか。
そのシェアを誰かに「伝えること」にどのような意味があるのか。
また、あるシェアを「目指すこと」にどのような意味があるのか。
これを考えてほしいのです。
たとえばアサヒビールは、自社商品『クリアアサヒ』を「麦の新ジャンルNO.1」とシェアトップであることをうたっていますが、実のところ酒税でカテコライズした時の「第3のビール」市場で見れば、キリンビールの『のどごし生』がシェアトップの商品です。
この場合のアサヒビールは、「第3のビール」市場をあえて原材料で細分化することにより、「狭い市場でトップ」とアピールしているわけです。
つまりシェアトップであることを消費者に「伝える」ことを、プロモーション戦略の手段として活用していることは明白です。
シェアではありませんが、「3年連続お客様満足度ナンバーワン!」のようなCMも、「ここがトップなんだ→だとすると安心して買えるな(間違いはなさそうだな)」という消費者心理を利用した同様の手法と言えるでしょう。
こうしたケースでの“市場シェア”は、「ブランド価値の向上」という重要かつ具体的な意味を持ちます。
では、自社のシェアを「知ること」には?
あるいは自社のシェアを社員に「伝えること」には?
ひとつの意味として、「モチベーションの向上」があるでしょう。
シェアが低いことを知り(知らせ)、危機感を植え付けることで上を目指すという考え方です。
これは確かに「アリ」だと思いますが、問題はしばしばこれが「単に尻を叩く」だけの道具になっていることです。
本来は危機感を植え付けるだけでなく、「なぜシェアが低いのか」を考えさせ、原因をピンポイントで特定し、そして解決策を考えさせるところまでセットにすべきです。
そしてそのためにも必要なのが、「なぜシェアが低いのか」という漠然とした問題を考えさせるのではなく、「本来はn%のシェアを取るべきだがそうなっていないのはなぜか」、つまりあるべき姿と現実とのギャップという『問題』を明確にした上で、その原因を考えさせることでしょう。
さて、そうするとそれを考えるためには「あるべき姿」、つまり本日の最初の問いである「何%を目指すべき?」について考えなければなりません。
次回はその考え方についてお話ししようと思います。
登録

人気の夕学講演紹介
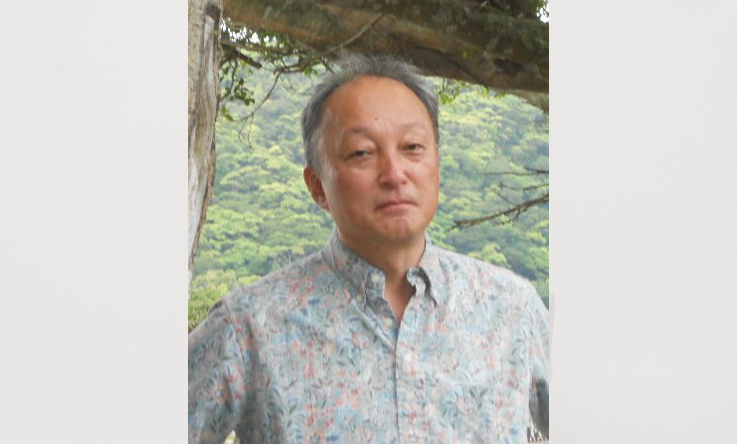
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
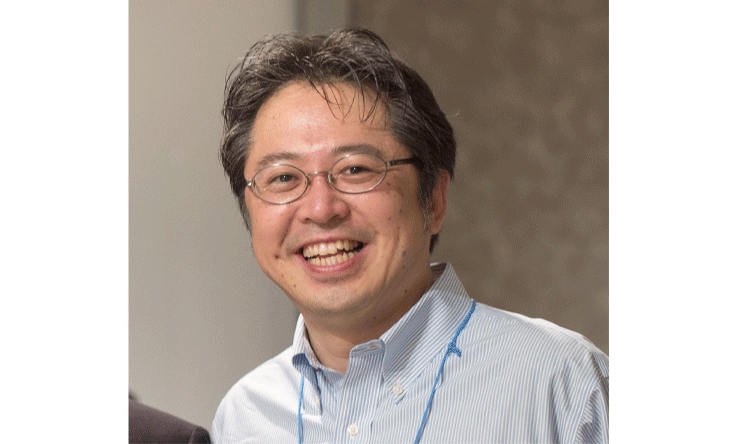
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




