ファカルティズ・コラム
2007年03月30日
“アコモデーション”を目指そう(前編)
当たり前の話ですが、仕事はひとりでやるものではありません。
会社等の組織に所属していれば、上司や同僚、関係部署と協力して仕事を進めますし、たとえフリーランスであっても、テンポラリーなチームで仕事に当たったり、またクライアントとのやり取りは不可欠です。
しかしこの他者との共同作業が、なかなかうまくいかないのが現実です。
複数の人間が集まれば、必ず(目に見えないものも含めて)なんらかの対立や葛藤、つまりコンフリクトが生まれてしまうからです。
特にビジネスにおける共同作業の場である会議室で、こうしたコンフリクトに悩まされたことがない方は皆無のはずです。
しかしながら、人間はひとりひとり異なる世界観を持っていますから、これは共同作業においてはある意味避けて通れない道なのです。
となれば、このコンフリクトへの対処の巧拙が、仕事のプロセスとアウトプットにも大きな影響を及ぼすことは自明であり、だからこそ会議におけるコンフリクト・マネジメントも包含する『ファシリテーション・スキル』が注目されているとも言えます。
さて、コンフリクトへの対処についてはファシリテーション関係の書籍でも必ず語られているように、実に様々な手法や考え方があるわけですが、本日はそのひとつとして、“アコモデーション”という概念を紹介させていただきます。
実はファシリテーションの講師としての私のベースは、ロジカルシンキングとSSMです。
ロジカルシンキングについては説明不要だと思いますが、SSM(Soft System Methodologyの頭文字)とは、英国ランカスター大のチェックランド教授が提唱した、課題発見から解決までの方法論です。
本エントリーはSSMの解説が目的ではありませんので、以下に参考となるWebサイト(PDFファィル)をご紹介しておきます。(ちなみに私のSSMの師匠の研究室のサイトです)
http://web.sfc.keio.ac.jp/~senoh/chousa/00/guide/pdf/311.pdf
そしてSSMにおいて、共同作業の必要条件として位置づけられているのが、“アコモデーション”なのです。
この言葉、「異なる世界観の同居」を意味します。
世界観とは、ある考えが成立するための前提条件のことであり、具体的には我々が持っている常識・価値観・マイルール・思いこみ・思考の枠組みなどがそれにあたります。
つまり、コンフリクトを生む要因としての個々人で異なる世界観を、否定したりするのではなく、それはそれで尊重した上で、うまく同居した状態にしましょう、というのがこのアコモデーションという概念です。
これでも今ひとつわかりにくいので、私自身この言葉を説明する際には、「時にはぶつかりつつも良好な、一つ屋根の下の嫁姑関係をイメージしてください(○○ブレンドのお茶のCMのような)」とお願いしています(笑)
人間は感情のイキモノです。また、生まれや育ちもひとりひとり違いますから、価値観や好みも千差万別です。だからどんなに論理的(筋が通った)な主張をしても、万人が受け入れるはずもありません。だからコンフリクトが生まれるのです。
そう考えると、このアコモデーションという概念、様々なコンフリクトの場面で活用できることがおわかりいただけるはずです。
特に、対立の構図において「どちらの主張も筋が通っている(論理的)」かつ「感情的な対立は無い」かつ「主張の中身の誤解も無い」ような、最もやっかいなコンフリクトの場合に有効でしょう。
私自身は、アコモデーションとは共同作業のシナジーを加速させ、そして組織内のダイバーシティまで実現する、非常に優れたコンセプトだと考えています。
ある意味、曖昧さを許容し、高コンテクストにコミュニケーションを行う、我々日本人のメンタリティにピッタリな考え方とすら言えるのではないでしょうか。
さてしかし、ここで皆さんは当然の疑問を持たれるはずです。
「確かに異なる世界観を同居させられれば、無駄なコンフリクトも減って共同作業は円滑に進むだろう。でも、じゃあどうやってそのアコモデーション状態を作ればいいんだ?」
この疑問に対する私なりの回答は・・・来週の後編で!
登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)
18:30-20:30
音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性
廣津留 すみれ
ヴァイオリニスト
音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介
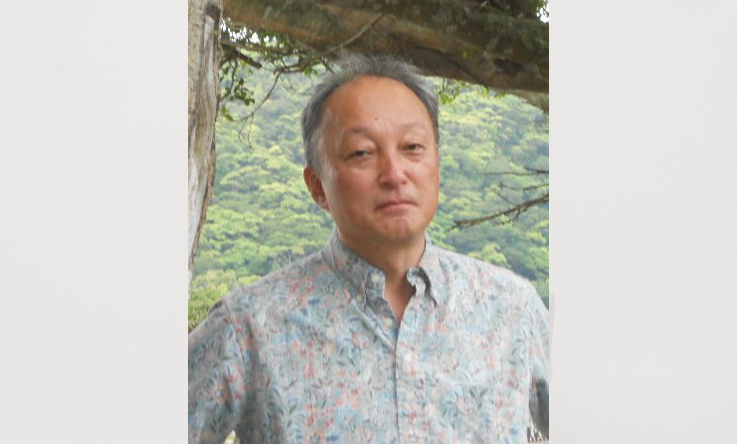
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
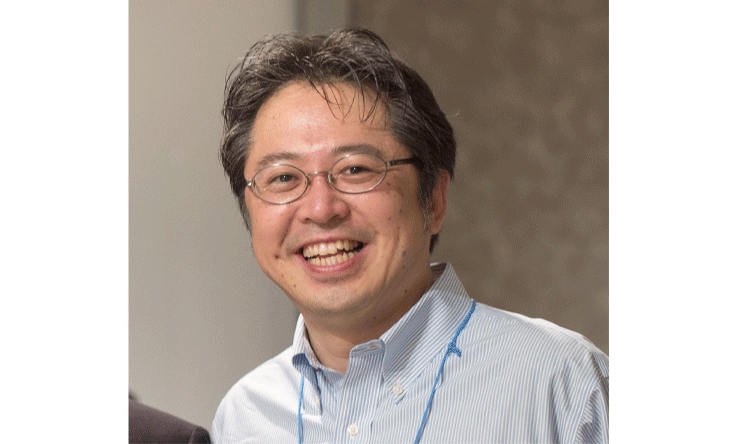
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。
登録




