ファカルティズ・コラム
2015年07月07日
民度の高さも考えもの
「利己主義」と「利他主義」という言葉があります。
要するに自分の利益を優先するか、他社の利益を優先するか、ということであり、しばしば前者は「彼はエゴイストだから」のように侮蔑的な扱いになります。
しかし、そもそも「真の利他主義」などあるのでしょうか?
「他者のために」という意識や行動の奥底には、「そんな俺かっこいい」とか、そこまでではないにしても「人はかくあるべき」という理想に近づくという『個人の利益』の追求があるのではないでしょうか。
まあ、こんなことを言うと、また「へそ曲がり」と言われそうですが(笑)
さて、実は本日はそんな皮肉めいた主張をしたいわけではありません。
利己主義と利他主義。しかしそれと似て非なる切り口で考えると、とても日本人らしい気質があると思うのです。
それを「他者に迷惑を掛けない主義」とでも呼びましょうか。
利己主義や利他主義の「利」とは、ある行動が自分や他者に与えるプラスの影響です。
よって行動のにはもうひとつのマイナスの影響、つまり「迷惑」もあります。
この迷惑が「自分に及ぶのを回避する」のか、それとも「他者に及ぶのを回避する」のどちらを志向するのか。
これも利己主義/利他主義と同様、対概念として成立します。
そして私たち日本人は、この「他者に迷惑を掛けない主義」の傾向が強い。
ルールやマナーの遵守などから、よく「日本人の民度は高い」と言われます。
これ、まさに私たちが「できるだけ他者に迷惑を掛けないように」とすり込まれ、それが行動に表れているからではないでしょうか。
しかし、本日2度目の問題提起。
本当に私たちのこの気質は「良いこと」なのでしょうか?
確かに社会の秩序という点において、この「他者に迷惑を掛けない主義」はプラスに働きます。
いや、この気質は社会秩序を維持する基盤と言ってもいいでしょう。
たとえば公共交通機関の過密かつ複雑な運行は、私たちにこの気質がなければ成立しません。
しかしこのブログでも幾度となく述べているように、モノゴトには必ずプラスとマイナスの二面性があります。
「迷惑」とは「リスク」と言い換えることができます。
「他者に迷惑がかからないようにする」とは、自分の行動が他者に対してどのようなリスクとなるかを事前に察知し、そのリスクが顕在化しないようにする、ことです。
リスクに対して敏感なのは決して悪いことではありません。
ましてや他者に対するリスクを早めに察知することは、トラブルを防ぎ、円滑な人間関係を維持することに繋がります。
しかしだからこそ、この気質は問題も孕んでいます。
それは「守りの姿勢になり、攻めに転じにくい」ということです。
「迷惑を掛けない」とは、まさに「トラブルを避け、現状を維持する」ことに主眼が置かれるからです。
ひとりひとりで考えれば、さほど大きな問題にはならないかもしれません。
しかしそのひとりひとりが集まった「組織」や「社会」という集合体で考えると、この「守りの姿勢」にはデメリットも多いはず。
「仕組みをこう変えたい。しかしそうするとあの人の顔を潰すことになるからやめておこう」
「この事業から撤退すべき。しかしそれで既存ユーザーが困るから続けなきゃ」
これでは変革やイノベーションなど起きるわけもありません。
日本企業がイノベーションを起こせなくなった大きな理由のひとつに、この「他者に迷惑を掛けない主義」があるというのは、私の考えすぎでしょうか。
民度の高さは維持しつつ、柔軟に「他者への迷惑はごめんなさいと割り切る主義」も必要だと思うのです。
登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)
18:30-20:30
音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性
廣津留 すみれ
ヴァイオリニスト
音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介
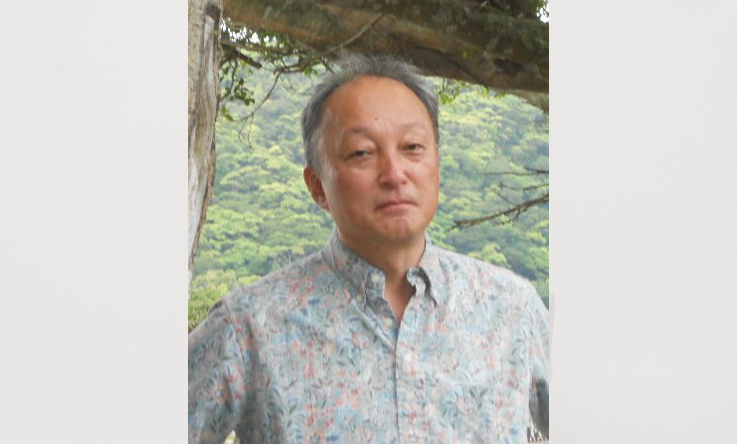
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
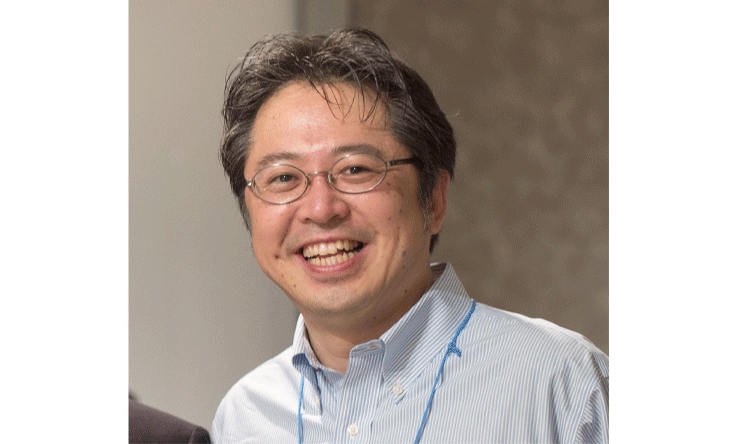
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。
登録




