ファカルティズ・コラム
2007年09月22日
その仕事は何のために?
今回は、先月のエントリー『他者への仕事の頼み方』の具体例と言えるお話です。
昨日ある駅でこんなシーンを見ました。
駅のホームを掃除する男性。そこに電車が到着し、大勢の乗客が降りてきました。
ところがその男性は意に介さず、狭いホームで掃除をし続けています。そのため人の波がそこでつかえてしまい、電車から降りられない人がいる(そしてもちろん乗ることができない人もいる)ため、電車もなかなか発車できません。
その男性がホームの反対側に少し寄るだけで、その状態は解消されるのです。しかしそれでもまだ掃除を続けようとします。
不思議な光景でした。
なぜ彼は乗客の邪魔をしてまで、掃除を続けようとするのでしょう?
もしかしたら、彼の方が乗客達に対して「仕事の邪魔だ」と思っていたのかもしれません。事実、乗客が人の波の中で彼にぶつかった時、彼は何度も舌打ちをしていました。
さて、そもそも『ホームの掃除』という仕事は、何のために行うものなのでしょうか?
それは、「乗客に気持ちよく駅を使ってもらう」ためではないでしょうか。
つまり『ホームの掃除』とは、「乗客に気持ちよく駅を使ってもらう」ための手段であって、決してそれ自体が目的ではないはずです。
彼もそれが認識できていれば、昨日のように乗客の邪魔をするという「目的に反した行為」はしなかったはずです。
まさに『本末転倒』。
しかし私はそれは彼1人に問題あるとは考えていません。
仕事の与え方にも問題があるのです。
仕事の内容とやり方を教える時に、なぜその仕事の意味も併せて説明しないのでしょうか。1分もかからないはずなのに。
仕事を与える立場の人間は、「そんなわかりきったことを…」と思いがちです。
しかし、その「わかりきったこと」がわかっていない人は、思った以上に多いのです。
考えてもみてください。本当に全員がわかっているのなら、企業の行動指針やコンプライアンス部門は不要のはずです。
今一度、ご自分の仕事は何のためなのかを考えてみてください。
そして誰かに仕事を与える時には、その仕事の意味も説明してあげてください。
登録

人気の夕学講演紹介
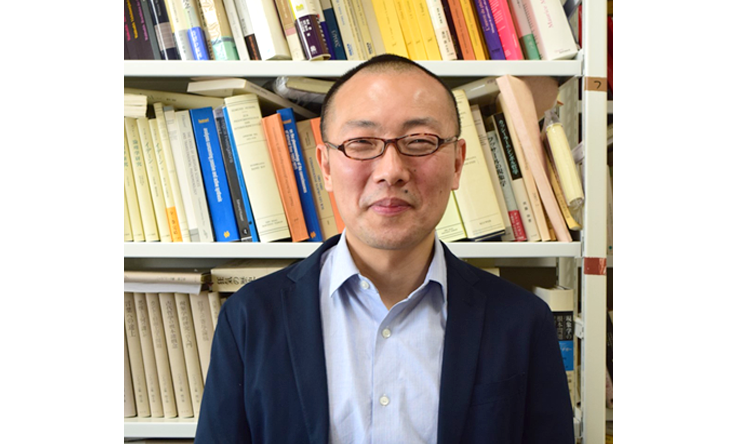
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
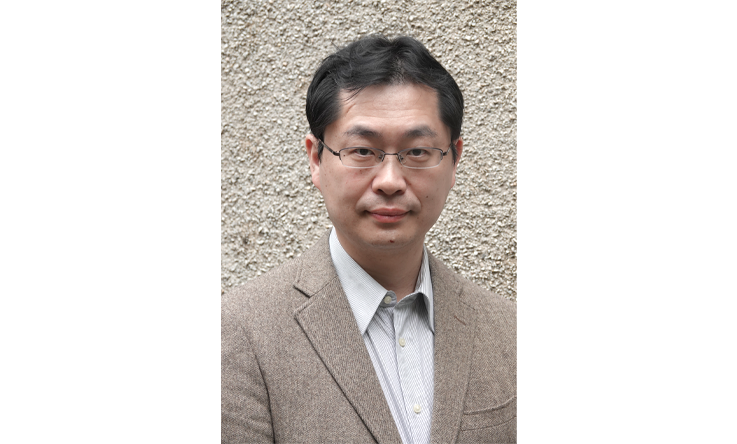
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




