夕学レポート
2008年07月04日
ロボットを通して人間を考える 瀬名秀明さん
東北大の大学院でミトコドリアの研究に勤しんでいた瀬名秀明先生が、バイオホラーの傑作と言われる『パラサイト・イヴ』でデビューしたのは、博士課程在籍中の13年前のことでした。
太古の昔に存在していた利己的遺伝子「イヴ」が、何億年に及ぶ生物寄生の眠りから覚め、ヒトに対して反乱を企てるというものです。
ミトコンドリアDNAの解明にから導かれた、人類最古の人類が、数万年前に北アフリカに生まれた女性であったという最新知見をベースにしたホラー小説でした。
この作品を期にSF作家としての活動もはじめた瀬名先生が、ロボットの世界に関心を持ったのは、文芸春愁から依頼されたサイエンスルポがきっかけだったそうです。
「ロボットは人間を越えられるか」をテーマに掲げ、ロボット研究の最前線を追った長期取材でした。
その取材をきっかけに、ロボット研究への理解を深めた瀬名先生が気づいたのは、ロボット研究が、SFやアニメ等の空想世界におけるロボット文化と相似形をなしながら進化してきたという事実だそうです。
瀬名先生によれば、ロボット研究には大きく二つの流れがあるそうです。
ひとつは、「人に寄り添い、近づくことを目指す」タイプ。いわゆるヒューマノイドと言われるもので、アニメでは鉄腕アトム、リアルワールドでなら、ホンダのアッシモに代表されるタイプです。
このタイプのロボット研究は、人の気持ちがわかることを究極目標に進化をしているそうです。
いまひとつは、「人間にやらないこと(やれないこと)をやる」実用タイプ。鉄人28号がアニメの典型で、現実の世界では、お掃除ロボットやレスキューロボットがこの流れに位置づけられるでしょう。
世界のロボット文化に多大な影響を与えたSF作家のアイザック・アシモフのロボット小説を丹念に読み込んでみると、この二つのタイプのロボットを巧みに描いていることがわかると瀬名先生は言います。
また、アシモフが残した「ロボット三原則」は、ロボットとは何かを規定する意味で、その後のSF作品に大きな影響を及ぼしたと言われているそうですが、瀬名先生によれば、アシモフは、最初から「ロボット三原則」を考えたわけではありませんでした。
上記の二つのタイプのロボットを空想しながら、ロボットと人間の共存のありようを、小説を書くことでスタディし、本質に近づいていったものだ、そうです。
アシモフがロボット小説を書くことは、人間とロボットの違いを見つける旅であり、それは取りも直さず、「人間とは何かを考えること」に他ならなかったというわけです。
アシモフの思考の変遷は、現代のロボット研究者の関心と重なるそうです。彼ら(ロボット研究者)は、いちように生命科学にも関心が高いそうです。それはロボット(マシン)が人間になりうるか、を考えることに通じるからです。
先日の夕学で、福岡伸一先生がいみじくも指摘したように、「生命とは何か」という命題には、いまも「機械論」と「動的平衡論」が並立しています。
生命科学の専門家でさえ、「生命」の定義をまとめることができないでいる深遠な問題でもあります。
ロボットとは何かを考えることで、人間とは何か、生命とは何かという崇高な思考の隘路にはまって動けなくなるとき、それをブレークスルーしてくれるのが、SFやアニメの世界で創造力豊かに描かれる空想世界のロボットイメージです。
ロボットは、科学者やエンジニアが作ってはいるが、創造してはいない。
ロボットは、空想の世界で着想され、それを科学者やエンジニアが形にすることで進歩してきた。
瀬名さんは、そんなことをおっしゃいました。
だとすれば、ロボットの未来を考えることは、我々がロボットに抱く、期待と恐怖、違和感と親近感、恐れと憧れをしっかりと見据えることからはじまるのかもしれません。
登録

人気の夕学講演紹介
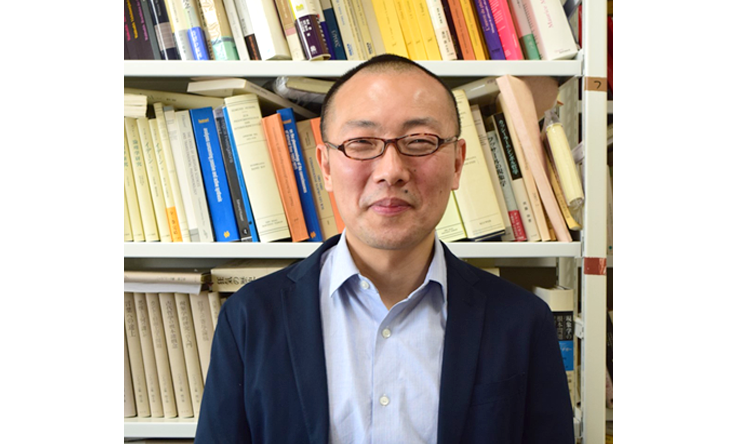
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
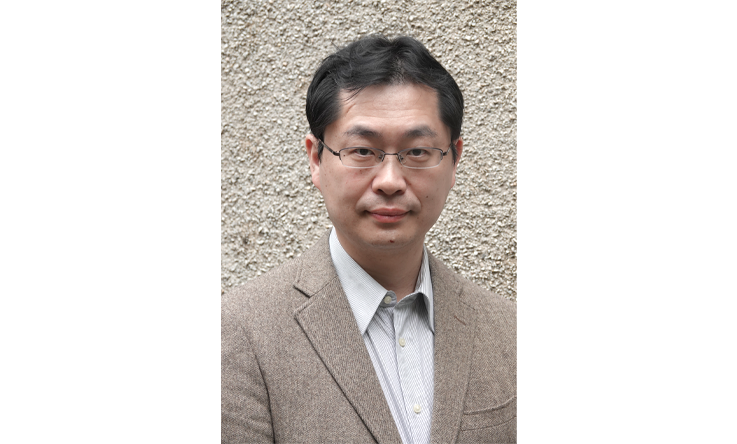
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




