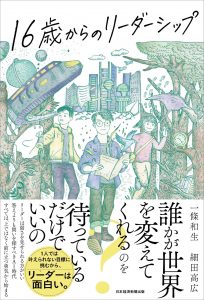ピックアップレポート
2025年11月11日
一條 和生・細田 高広著『16歳からのリーダーシップ』
リーダーとリーダーシップは何が違うのか?
「リーダー」とは先頭に立つポジションを意味する言葉です。ですから部長やキャプテンや委員長は確かにリーダーだと言えそうです。一方、「リーダーシップ」はどうでしょう。そもそも英語の「-ship」という接尾語は名詞にくっつくと、それを成立させる大切な性質や役割を示す言葉になります。例えばFriend は「友人」ですが、Friendshipはそれを成り立たせる「友情」という意味になります。Sportsmanなら「運動家」ですが、Sportsmanship と言えば、運動家にとって重要な「正々堂々と向き合う姿勢」を指します。同様にLeadership とはLeader を成立させるための大切な性質と役割、つまり、目標に向けてチームを導くことを意味するのです。
リーダーシップを発揮するのはリーダーの役職を明確に持っている人だけに限りません。優れた組織やチームは、さまざまな個性を持つ人たちが、場面ごとに次々と異なるスタイルのリーダーシップを発揮することが知られています。
高校3年生の引退がかかったサッカーの試合を想像してください。チームは1点差で負けている状況で、試合時間は残り2分。誰もが勝利を諦めかけています。ずっとチームを引っ張ってきたキャプテンさえ俯いている。みんなの足が止まる中、声をあげたのはただひとりの1年生レギュラーでした。彼は「まだまだ行ける!」と先輩たちを励まし、最後の力を振り絞って自らドリブルで敵陣に仕掛けていったのです。その行動が周囲を勇気づけ、同点ゴールのきっかけになりました。これと似たような奇跡は、きっと皆さんの学校生活に溢れていることでしょう。
このエピソードでは、奇跡の逆転勝利のきっかけをつくったのはキャプテンではなく、唯一の下級生でした。最後まで諦めずに勝利を信じ、自ら率先して周囲を導こうとした。ひょっとすると1年生だったからこそ、重圧のかかる3年生とは違う視点で物事を考えられたのかもしれません。いずれにしてもこの瞬間、目標に向かってチームを導く役割を果たしました。この1年生はキャプテンというリーダーではなかったけれど、確かにリーダーシップを発揮していたと言えます。
必要な時に本当の意味でリーダーシップを発揮できる。そういう人が学校生活でも、その先の社会生活でも、必要とされる人になるのです。どんなに頭が良い人がいても、何かの才能に秀でた人がいても、誰かがその力をすべて引き出し、ひとつに束ねて、大きな目的の達成に向かわせられなければ、世界には何も生まれません。
多様性の時代にこそ率いる力が必要
いまの時代、リーダーシップがこれまで以上に大切になってきています。要因のひとつは、多様性が求められる時代になったことです。ひとりひとりの違いを認める時代に、ひとりが発揮するリーダーシップが求められるなんて、逆説的に感じられるかもしれません。けれど、多様性に溢れる社会という理想は、強いリーダーシップがなくては、絵に描いた餅で終わってしまう可能性が高いのです。
例えば、多様性に溢れたインターナショナルな学校をひとつ想定してみましょう。
生徒は世界各国から集められ、人種も言語も宗教もバラバラな上、ジェンダーにしても男女だけでなくLGBTQを含めてあらゆるグラデーションが存在します。また障がいを持つ生徒もたくさんいるとしましょう。
そんな学校で暮らすことはある面では理想的です。日々、新しい考えに出合うことができます。まったく新しいアイデアが創発されるかもしれません。うまくいけば特定の人種やグループを優遇することなく、誰ひとり取り残されない学校生活がつくれるはずです。
しかしながら、この学校を運営するためには困難がつきまといます。例えば、給食の献立をひとつ決めるのにも苦労するでしょう。生姜焼きを給食に出そうとすれば、豚を食べないイスラム教徒は猛反発します。では牛にすれば良いかというとそれもNGです。ヒンドゥー教徒は牛を食べません。じゃあ鶏肉にしようとすると、そもそもヴィーガンの人は肉は食べないというのです。いっそ全員に野菜だけと決めてしまえば、特定のグループを優遇しているという批判を浴びることでしょう。
実際、インターナショナルな会食を開催するのは、大変な困難がつきまといます。
参加者ひとりひとりの食べられるものを事前にヒアリングしてメニューを個別に準備し、そのレストランで調達できない場合は、他のレストランにも協力してもらったり、特別なシェフを呼んだりすることもあります。日本人だけの食事会を開催するのとは異次元の難しさです。
給食ひとつでこの騒ぎですから、みんなが平等に参加できる運動会のルールや種目を決めるのも、性自認やジェンダーに合わせたトイレの数や種類を決めることにも、大変な苦労を伴うことでしょう。また放っておけばグループに分かれてしまい、お互いに交わろうとせず、争いを生むリスクもあります。対立する状況を乗り越えて意思決定をしていくためには、強い意志を持ちながら、ひとつ上の視点で対立を乗り越えていく個人が欠かせません。ひとりひとりの個性を大切にする。そのためにもいま、かつてないほどにリーダーシップへのニーズが高まっているのです。
自分らしいリーダーシップへ
リーダーシップの研究者たちは半世紀以上にわたって、一流のリーダーに共通しているスタイルや特性や性格、つまりリーダーへの「向き、不向き」を明らかにしようとしてきました。けれど、結論から言えば、リーダーに共通する条件と呼べるものは、ひとつもなかったのです。
研究者は優れたリーダーシップには型があるのだ、という考え方自体が間違えていたと考えざるを得なくなります。そう、リーダーに向いている人なんていないのです。逆説的ですが、それはリーダーシップ研究の最大の発見と言っても良いでしょう。現在では、誰かの真似をするのではなく、ありのままの自分を表現できている人こそが、人に信頼され、信じられ、影響力を手にしていることが分かってきました。
古典を学ぶ大切さ
この本が読者の皆さんに気づきを与えて、皆さんそれぞれが自分の得意な分野、好きな分野で、自分にできる課題解決の先頭に立ち(リードし)、素晴らしい日本、世界が実現する一助になることを心から願っています。
課題解決に取り組むにあたっては、それまでの経験や知識が役に立たないような事態に直面することもあるかもしれません。今まで経験したことのないような変化に遭遇して、どうしたらいいのか、途方にくれてしまうこともあるでしょう。しかし立ち止まり続けることはできません。時代は常に動いていきます。新しい変化に遭遇しても考え、判断し、動き出す必要があります。それでは、そのような時に、どうしたら「正しい判断」を下すことができるのでしょうか? そもそも「正しい判断」とはどういうものなのでしょうか? 今までに経験したことがないことですから、参考にできるデータもありません。未知のことですから、AIも役に立ちません。
ここに、いつの時代も、古典(クラッシックス)に立ち返る意義があります。古典には時代を超えた普遍が示されています。皆さんは、古典を単純に古いものだと思っているかもしれません。大間違いです。古典は今に活きるものです。2025年の今でも、500年以上前に描かれたと言われるレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」を見ると、私たちはジョコンダ夫人の口元に微かに浮かぶ微笑みに魅了されます。今から400年以上前にシェークスピアが書いた『ヴェニスの商人』を読むとワクワクします。裁判の場面で、ポーシャが恋人アントーニオのために弁護士に扮装し、借金のかたにアントーニオの肉1ポンドを切り取ってもいいが、血は一滴も流してはいけない、といって恋人の命を救う場面は、実にドラマチックです。古典は今でも人の心を動かします。加えて、時代を超えた変わらない普遍、つまり教養(リベラル・アーツ)を学ぶことができます。古典を読み続けることによって、何が人間にとって正しいのか、人間にとって楽しいこととは何か、何が人間を幸せにするのか、つまり人間にとって何が本質なのかを理解する基盤が、だんだんと皆さんの中に養われていくのです。経験したことのないような事態に遭遇した時、時の試練を耐え抜いた普遍的な価値基準ほど心強いものはありません。
一條は3年ほど前に、ある教育関連の会社から「私をつくった一冊」というコラムへの執筆を求められました。つまり、自分がリーダーシップやイノベーション、そしてグローバル化を研究する学者になるにあたって最も影響を受けた本の紹介を依頼されたのです。私が迷うことなく選んだのは、フランス人のジュール・ベルヌが記した『二年間の休暇』でした。経営に関する本を選ぶと予想されていた担当の方は、「まさかこの作品を取り上げられるとは!」と大層驚かれました。小学校高学年を対象とした本が紹介されれば、驚くのも不思議ではないですね。
『二年間の休暇』は、日本では『十五少年漂流記』という邦訳名でも知られています。ニュージーランドの寄宿学校で学ぶ十五名の少年が嵐の中、無人島に流されてしまいました。誰もいない無人島での生活という絶望的な状況に遭遇しながらも、彼らは希望を失わず、創意工夫とチームワークを発揮して2年間の生活を無事に終えたのです。胸がワクワクする冒険小説です。オリジナルは1888年に出版されました。世界中で長きにわたって読み継がれている古典の名著です。
私が『二年間の休暇』と出会ったのは10歳の時でした。その年、福音館書店から福音館古典童話シリーズの第一巻として、オリジナルタイトルの完訳『二年間の休暇』が出版されました。ページ数で525ページ。本の厚さは4センチです。持つとずっしりと重いカラフルな表紙の本が、ベージュ色のカバーボックスに入れられています。今でも手にすると、特別な本という感じがします。当時、小学校5年生になったばかりの自分がどうやってこの本を入手したのかはよく覚えていません。しかし、読書を愛し、私にも本を読む喜びを教えてくれた父が買ってくれたのだと思います。
私は分厚い『二年間の休暇』を、あっという間に読み終えました、そして今でもときどき手に取ってみる、大好きな本です。その度にワクワクします。何しろタイトルが魅力的です。2年間も休みがあるなんて、なんて素敵なことなのだろうと思いました。しかし、本を読み進めると、自分が住む世界(日本)とはまったく異なる世界があることを知って驚きました。2年間の無人島での漂流生活を体験した子どもたちは当時の私と同世代。彼らはニュージーランドの寄宿学校で学んでいて、そこではイギリス人、フランス人、アメリカ人など、さまざまな国々の子どもたちが学んでいました。日本人だけで学んでいる自分とは別世界でした。自分には知らない世界があるのだな、と思いました。そしてそういう世界をもっと知りたいと思いました。グローバルな世界との出合い、関心の高まりでした。
本を読み進めてさらに驚いたのは、子どもたちの行動です。十五人の少年たちは大統領を選ぶことになり、最年長で思慮深いアメリカ人のゴードンが初代大統領に選ばれました。ゴードンは生活の日課表をつくり、午前と午後の2時間ずつを学習時間に充てる、年長の少年たちが交代で教師役を務める、少年たちに炊事洗濯を分担させ、寒暖計や気圧計の記録係、日付の記録と時計の管理者を定めるなど、規律をつくり上げていきました。こうして、島での生活は次第に軌道に乗っていきました。まさにリーダーシップの発揮でした。2年間の休暇を経て、十五名の少年は大きく成長していったのです。
『二年間の休暇』に書かれた世界に私は魅了されました。10歳の私は、それがなぜだったのか分かりません。しかし、今はっきりしていることは、当時の興味が後に私の専門分野となったグローバリゼーションやリーダーシップの研究につながっているのだということです。『二年間の休暇』は私の土台を築き上げてくれたのだと思います。
どんな事態に陥っても、未来に希望を持ち、自信を持って、危機を克服していく、という人生にとって大切なことについても教えてくれています。
生活を変えて、リーダーシップの旅に旅立つ
世界で政治的、宗教的対立が激化し、多くの人々が、とりわけ子どもたちが犠牲になっています。その事実に心を痛めます。歴史に学び「正しい判断」を下すことが、決して容易ではないことも、現在の世界的な対立状態が示唆しています。しかし、だからと言って、何が人類にとって正しいのか模索することをやめてはいけません。考えの違いを退けるのではなく、なぜ違いがあるのかを理解しようとする。その中から、対立を解消する道も見えてくるのではないでしょうか。簡単なことではないですが、それを私たちはやり続けないといけないのではないでしょうか。自分の国の歴史を学ぶのと同じくらい、他国の歴史を学ぶことも、皆さんには続けてほしいと思います。
歴史を勉強して美術館に行く。古典を読んでみる。そうした生活を続ける。その中で皆さんには、本質を見極める眼が養われていきます。キツネが星の王子様に教えた、大切なことをハートで見ることができるようになります。芸術を鑑賞すると、本を読むと、自分の知らない世界がどんどんと自分の中に入ってきます。それによって皆さんの考え方、生き方、そして日々の暮らしが変わるのではないでしょうか。それが皆さんらしいリーダーシップ発揮の第一歩です。皆さんのリーダーシップの旅に幸あれ!
Good luck to your leadership journey!
『16歳からのリーダーシップ』(日本経済新聞出版 2025年5月)を一條氏と出版社の許可を得て抜粋・編集しました。無断転載を禁じます。
※日経BOOKプラス まいにち「はじめに」より「はじめに」と「目次」をご覧いただけます。

一條 和生(いちじょう・かずお)
IMD教授
慶應MCC『グローバル・リーダーシップ』プログラム担当講師
1958年東京生まれ。一橋大学大学院社会学研究科、ミシガン大学経営大学院卒業。経営学博士(ミシガン大学)。専攻は組織論(知識創造論)、リーダーシップ、企業変革論。
知識創造理論に基づいて、リーダーシップ、企業変革に関する教育・研究活動を進める一方、現在、日本ならびに海外の一流企業のリーダーシップ育成プロジェクト、コンサルティングに深くかかわる。日米の数多くのリーディング・カンパニーで長期的な経営者育成プログラム、企業変革プロジェクトを設計、指導している。グローバルに行っているエグゼクティブ教育が評価され、同分野では世界トップと評価されているビジネススクールIMD(スイス、ローザンヌ)の教授に日本人として初めて就任(2003年)。一橋ビジネススクールでの教授としての活動と並行して客員教授としてIMDで教えていたが、2022年4月に13年ぶりにフルタイム教授としてIMDに復帰し、グローバルなエグゼクティブ教育に携わっている。
現在、(株)シマノ、(株)電通国際情報サービス、ぴあ(株)の社外取締役を務めるほか、IFIファッションビジネススクール学長も務める。
[担当プログラム] 『グローバル・リーダーシップ』(2026年2月)
登録
登録