夕学レポート
2012年01月20日
簡単にわかった気になってはいけない 川田順造さん
「ルビンの壺」と呼ばれる錯視図形がある。企業研修で、モノの見方・考え方の多様性を促す比喩として使われるので、ご存じの方も多いであろう。

「ルビンの壺」の原理は、地と図の転換である。
視点を地の部分(上記でいえば黒い部分)に置けば、向き合った人間の顔に見えるし、図の部分(白い部分)に視点を落とすと壺に見える。
「日本とはどういう国か、日本人とはどんな人間か」という問いもこれに近いもの、というより、「ルビンの壺」を二次元ではなく、三次元、四次元にまで複雑化したものと言えるかもしれない。
これが日本的と思っていることも、視点を変えて観察してみると、異なった絵姿に見えてくる。
「日本とはこういう国です」「日本人とはこういう人間です」
ということを簡単に言えるほど単純なものではない。
川田先生の話を聞いて、つくづくそう思った。

日本のグローバル化は、その逆説的効果として、「自分達は何者か」を語ることを要請する。かつては、ひと握りの知識人に任せておけばよかった日本と日本人に関わる説明責任を、われわれ普通のビジネスパースンも担わねばならなくなった。その必然として、日本と日本人の深層に対する関心は高まっている。
そんな問題意識もあって、agoraではこんな講座も開催したほどだ。
『田口佳史さんに問う【東洋思想と日本文化】』
今回の夕学も、「人類学の知見から見た日本論」というビッグピクチャーを見せてくれるのではないかという素人発想の期待を持っていた。
そんな期待を見事に裏切ってくれた。
「簡単にわかったような気になってはいけない」
川田先生に、そうたしなめられたような気がする。
川田先生は、ご自身のフィールド調査の知見を交えて、「日本的なるもの」の地と図の転換例を示してくれた。
代表的な日本人気質として挙げられのは、「ムラ社会、団結力、同質性、共同に強い、骨身を惜しまず働く、ひとつの土地に執着する、排他的等々」といったものであろう。
これらは、良くも悪くも「米」に執着してきた社会が培ってきた特徴である。
つい150年前まで、日本は「米経済システム」であった、藩の財政規模も、武士の報酬も全て米に換算して評価された。
宮沢賢治の「雨ニモマケズ」には「一日に玄米四合と、味噌と、少しの野菜を食べ….」という一節がある。庶民も、米をたらふく食えることが、なによりの幸せであった。
稲作は、人を土地に縛り付ける。狭い土地を究極まで活用し、皆で力を合わせて、手間ひまかけて、生産性を高めることを求める。
こんにち、「日本的なるもの」と呼ばれている多くの特質は、稲作に執着することによって形成された。
しかし地と図を転換すれば、稲作が伝わる前の縄文人=原日本人は、そうではなかったとも言える。
川田先生は言う。
「縄文人は、もっと平和的で、おおらかで、力強かった」
獲物を求めて野山を駆け回っていた縄文人の身体的特徴は「エクステンション的」であったという。腕力が強く、上半身に重心をかける生活行動をしていた。
原日本人=縄文人の特徴を受け継ぐ、アイヌや沖縄の伝統的な生活様式を研究してみると、エクステンション的な身体の使い方が散見される。
弥生人の血が濃い本土の人々が、足腰の重心を置くプル型の生活行動をしていたのとは明らかに異なる。
「アイヌや沖縄の生活行動は、フランスの田舎に近い」
フランスで10年近く滞在研究を行ってきた川田先生の見立てである。
機械が導入される以前の荷物の背負い方、農作業の仕方を調べると、アイヌや沖縄の人々とフランスの農夫は、いずれも上半身の重心を置き、腕力を使って田畑を耕していたという。
つまり原日本人=縄文人は、ガリヤと呼ばれ、未開の蛮族の地とされたローマ時代の大陸欧州と共通する生活様式を持ち、価値観をもっていたのかもしれない。
川田先生は、18年前フランス政府から教育・文化功労賞を授与された。
その受賞スピーチで、こう語ったという。
「日本人は、フランスの良い部分、綺麗な部分、煌びやかな部分だけを見てきた。しかしフランスもひとつではない。片田舎の農村の暮らしを丹念に観察すれば、また異なった姿も見えてくるはずだ。」
日本を語ることが簡単ではないように、外国を理解することもまた簡単ではない。
登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)
18:30-20:30
音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性
廣津留 すみれ
ヴァイオリニスト
音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介
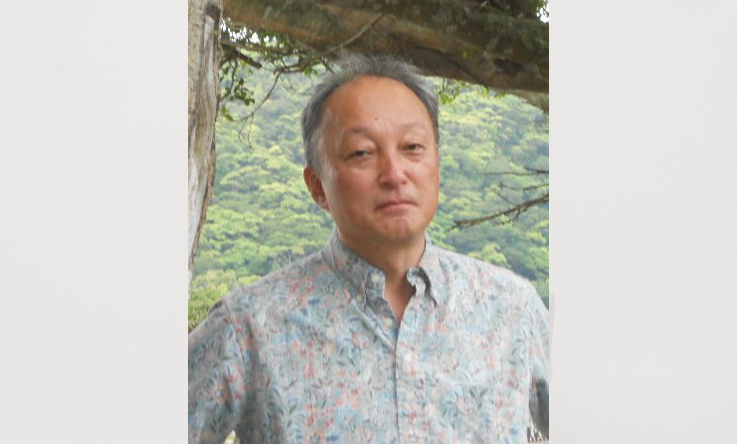
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
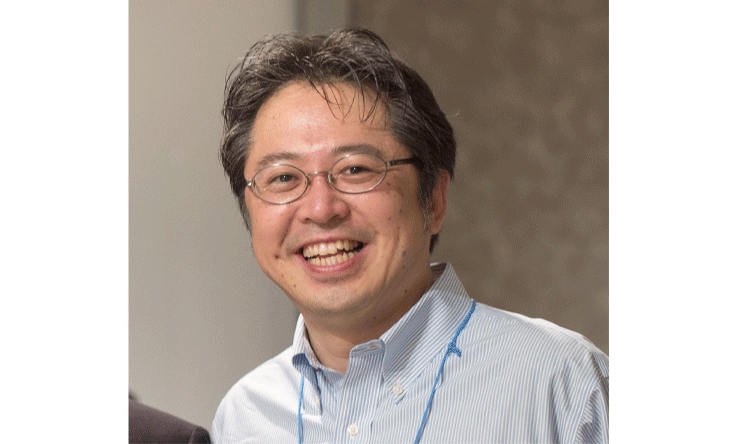
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。
登録




