2016年08月19日
「ルール」の本質
残暑お見舞い申し上げます。
シン・ゴジラ、観ましたか?
まだ観てない?
それはいけません。観に行きましょう。
さて、本日はそのゴジラとは全く関係ありません(笑)が、「ルール」というものについて。
「○○してはいけない」から、「○○してもよい」、あるいは「○○しなければならない」まで、私たちの周りには様々なルールがあります。
それは法律のような明文化され、必ず守らなければならない(と一般的に言われている)もの、そして明文化はされていなくても、守ることが「当たり前」とされている暗黙のルールもあります。
ルール、つまり「決まり事」は面倒なものですが、やはり社会の秩序という点で、こうしたルールはなくてはならないものです。
実は先日、この「ルール」について、「確かに!」と思わされることがありました。
それはムスメのこんな言葉から始まったのです。
「今日はお酒飲んじゃダメよ」

我が家には、こんなルールがあります。
「お酒は、休日と休前日、および飲み会等のイベントの時しか飲んではいけない」
「今日はお酒飲んじゃダメよ」
ムスメがこう言ったこの日は、休日でした。
だからルールに従えば、飲んでもいいはずです。
当然(酒好きの)私は反論します。
はい、我が家の「ルール」を振りかざして。
「え~っ? どうして? 今日は休みじゃん」
そんな私に、ムスメはこう言いました。
「ルールはね、その成立過程、つまり、なぜそのルールができたか、に常に立ち戻るべきなの」
「???」となる私に構わず、ムスメは続けます。
「そもそもなぜこのルールはできたか。それは当然、父ちゃん(私はこう呼ばれています・笑)の健康のためでしょ?」
「ここのところ休みと休前日が続いてる。だから毎日飲んでるよね?」
「そしてそれって健康にいいと思ってる?」
「そもそも健康のために作ったルール、であれば重要なのはルールそのものを守ることではなく、健康を守ることでしょ?」
「だから今日は飲んじゃダメ。はい論破」
………ぐうの音も出ません(汗)
結局この日、私はお酒をあきらめ、緑茶で夕食をとりました。
そしてムスメのこの説得に「確かに!」と思うと同時に、「これってルールの本質だよな」とも思ったのです。
重要なのは「ルールを守ること」そのものではない。
より重視すべきは「ルールがつくられた目的」なのです。
これは何も我が家のルールだけではありません。
たとえば、「歩きスマホはやめよう」も、ひとつのルールです。
では、これは何のためにできたルールなのか?
それはもちろん、「他者に迷惑を掛けないため」であり、「本人も怪我をしないため」です。
であれば、周りに誰もいない、そしてどう見ても安全上問題のない場所であれば、別に目くじらを立てるようなものでもないはずです。
考えてみれば、文庫本読みながら歩く人なんかは昔からいたわけで。
まあ、歩きスマホはやらないに越したことはありませんが。
他の例で言えば、「著作権法」も厳格なルール適用には私は反対です。
この法は、「著作権者の利益を守る」ために作られました。
だからTVで放映されたアニメを録画し、それを動画投稿サイトにアップロードするのはダメです。
後に出すDVDが売れなくなるリスクがありますから。
しかし、ニュース番組なら?
タレントさんの肖像権が関わってくるようなケースは別として、運営サイドにクレームを入れ、投稿された動画を削除して、なんの利益を守ったことになるのでしょう。
いちいちエゴサーチでそうした動画を探し出し、クレームを入れる。
それに要するコストの方が、よっぽど自社の利益を損なっていると思うのは私だけでしょうか?
そしてこれは法律や社会のルールだけではありません。
あなたの会社にも、そして業界にも、様々な明文化されたルール、そして暗黙のルールがあるはずです。
そうしたルールに何の疑問も持たず、なかば「ルールを守ること」を優先している。
それ自体に疑問を持ちましょう。
そもそも何のためにこんなルールがあるのか?
その「ルールの本質」に立ち戻りましょう。
そうすれば必ず何個もの「昔は意味があったが、今や何の意味もない」ルールが見つかるはずです。
そんなルールは…やめればいいのです。
登録

人気の夕学講演紹介
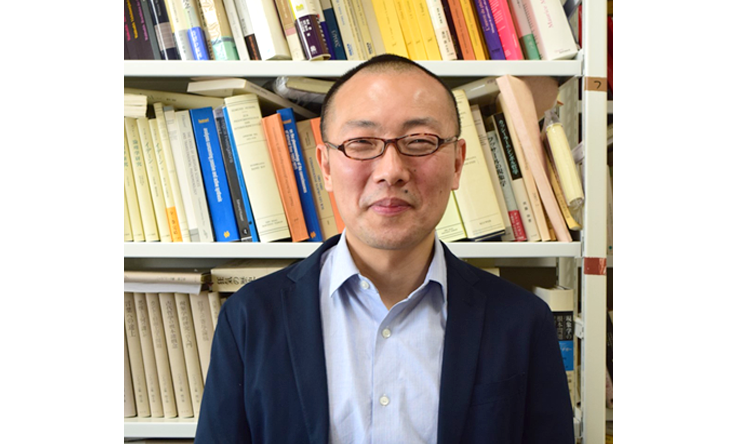
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
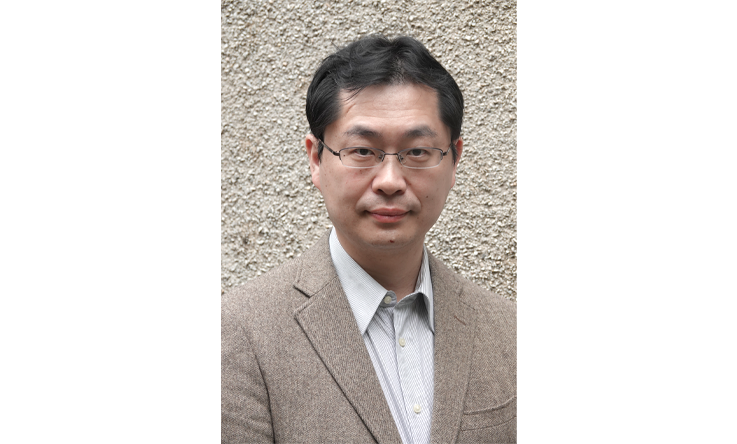
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




