ファカルティズ・コラム
2008年11月14日
反対語を考えてみよう
ネットでなかなか興味深い議論を見つけました。
A.『白い』の反対語は『黒い』? それとも『赤い』?
B.『水』の反対語は『油』? それとも『湯』?
どうも小学校の教科書では、Aは『黒い』でも『赤い』でも正解。Bは『油』が正解、となっているようです。
その正解に疑問を持った方が、塾の先生に「なんで?」と聞いたらしいのですが、「正解が決まっているから仕方がない」と言われたそうです。
皆さんはどう思われますか?
この時点で学校教育の問題点を指摘するのはやめておきます。
まずは上記の議論を論理的に分析してみましょう。
さて、この問題を考えるために重要なのは、「反対語の定義」です。
反対語と似た言葉としては、対義語・対意語・対語・反意語などがありますが、このブログで学問的定義を語ってもあまり意味はないと思いますので、あくまでも論理的見地(つまり筋が通っていればOK)から考えてみます。
思うに、“反対語”を、その厳密さで順番をつけると、
(1)科学的(できれば定量的)に対極にある言葉
(2)セットで使われることで、結果的に対極の存在だと感じさせる言葉
(3)一般的になんとなく対極にありそうな言葉
が、反対語の定義だと考えます。
(1)に該当するのが、『白い』の反対語の『黒い』でしょう。
「色味のない色の対極である白と黒」が反対語だというのは、確かに科学的です。
では『赤い』は?
これは「紅白」や「赤ワインと白ワイン」などから(2)と考えられます。
『水』と『油』も、「あのふたりは水と油」などという言い回しから、同じく(2)に該当します。
ただ、「液体の中で比重が重い/軽いか」という観点では、(1)とも言えます。
しかし液体の比重で考えれば、水より水銀の方が重いですし、油より軽いイソブタンなどもあります。そう考えると、同じ液体のカテゴリーで水と油が対極とは科学的には言えなくなります。
ところが『湯』は?
一件(3)の「なんとなく反対語」のようにも見えますが、「湯水のように」という慣用句から、(2)とも言えますし、さらに「同じH2Oでありながら、温度が高い/低い」と考えると、これは(1)に該当してしまいます。
そうすると「水の反対語は油より湯の方が科学的見地から適切だ」と言ってもおかしくない。
さあ困ったことになりました(笑)
もっと困らせてもいいですか?
『白い』の反対語である『赤い』。
では、『赤い』の反対語は? 『白い』だけですか?
『青い』も信号機の配置から(2)に該当します。
また、『青緑』も色相では『赤』の対極にありますから、完全に(1)の科学的反対語です。
そうすると『青』と『白』と『青緑』は類義語でしょうか?
違いますね。アタリマエです。
西を向いたときの反対と、南を向いたときの反対が同じのわけがありませんよね。
さて、このあたりで反対語の本質が見えてきたのではありませんか?
そう、反対語とは単に反対ではないのです。
世界の全ての(形のないものも含めた)モノゴトを表現する言葉を、なんらかの観点でカテゴライズし、そこにある座標(基準点)を設けた上で、その座標から等距離かつ対極にある言葉が反対語と言えます。
もう少しイメージとして考えてみましょう。
大きな方眼紙に適当にマルを描き、そのマルの中に点を打って、その点が真ん中に来る直線を引いてみてください。
そしてその直線の両端が・・・反対語です。
要は「どうカテゴライズするのか」「何を座標として定義するのか」さえ明確にできれば、どんな言葉にも反対語を設定することが可能なのです。
つまり、反対語を考えるには、『タイヘン論理的に』考えなければならないのです。
はい、小学校で反対語を教えるのは、実は『論理思考のトレーニング』の意味があるわけですね。
だから我々も、反対語を考えることで論理思考力を磨くことができます。
太宰治の「人間失格」には、主人公と友人が反対語で遊ぶシーンが出てきます。
太宰は、反対語を考えることが思考トレーニングであることを、感覚的にわかっていたのかもしれません。
それが国語の問題で正解かどうかはどうでも良いのです。
論理的にカテゴライズし、明確な座標軸を設定する「考えるプロセス」そのものが大事なのです。
あなたも様々な反対語を考えてみませんか?
『花』の反対語は?
『蝶』と答えたあなたは、少し年配の方でしょうか(笑)
『ゆめ』と答えたあなたは・・・「動物のお医者さん」とか好きでしたか?(笑)
「人間失格」では、『女』という答えが出てきます。
太宰ならではのカテゴライズと座標軸ですね。
ところで、小学校ではなぜ上記のような「反対語の考え方」を教えないのでしょうねえ。

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)
慶應MCCシニアコンサルタント
慶應MCC担当プログラム
ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎
デザイン思考のマーケティング
フレームワーク思考
イノベーション思考
理解と共感を生む説明力
大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタ®」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。
また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。
主な著書
『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社
『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年
『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社
『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年
『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年
『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年
『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版
登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)
18:30-20:30
音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性
廣津留 すみれ
ヴァイオリニスト
音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介
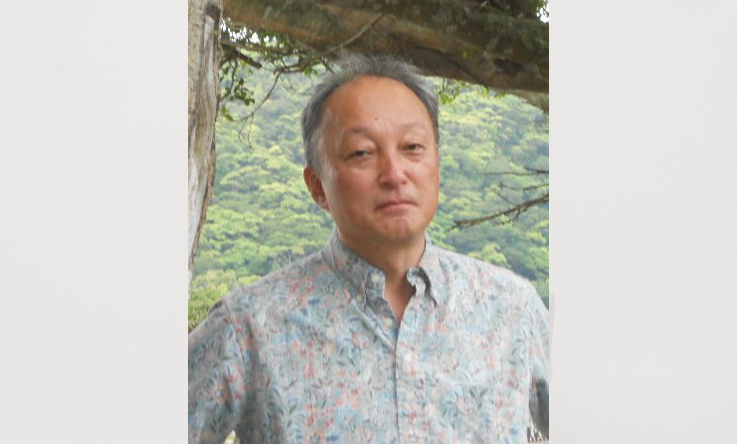
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
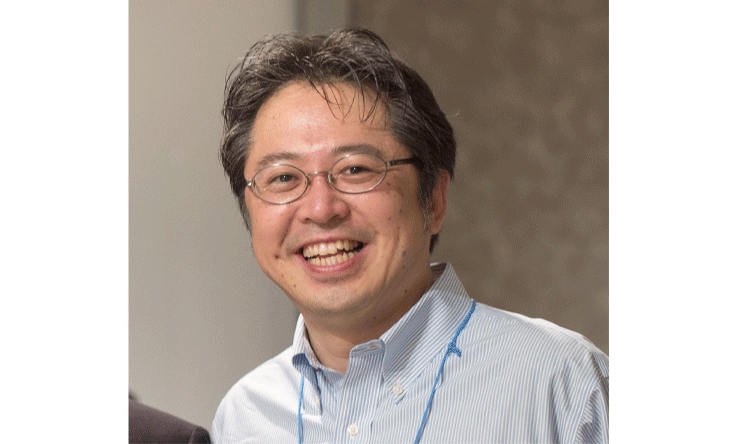
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。
登録




