夕学レポート
2008年05月28日
つつしみのこころ 小笠原敬承斎さん
小笠原礼法宗家のホームページによれば、小笠原氏は、清和源氏の流れをくみ、武家が勃興した平安時代後半から、東国で源氏の有力一門をなしてきた名家のようです。
小笠原氏が築城し、一貫して居城としてきた信州松本城は、信州出身の私にとっては、最も身近な史跡でした。また先代宗家の小笠原忠統氏が館長を務めていたという松本市立図書館は、受験勉強に通った場所でもありました。
更にいえば、福沢諭吉の自伝(福翁自伝)によれば、福沢家は、もともと小笠原氏に仕えていた下級武士で、江戸の初期に小笠原氏が九州中津に移封された際に、一緒に付いてきて、そのまま中津に根を張ったとのことです。
そんな不思議な縁も感じながらお聴きしたきょうの夕学でした。
さて、小笠原礼法は、室町時代に、京都において公家文化に対抗する「武士の定式」としてまとめ上げられたものだそうです。供奉、食事、宮仕えの応対の仕方、書状の様式、蹴鞠の仕方など、武士の一般教養を体系化されたものだそうです。
小笠原家には、室町時代から戦国時代に書けて著されてきた「小笠原礼書七冊」と呼ばれる伝書が残されています。
代々一子相伝の秘技として、将軍家や諸大名家にだけ伝えられてきた小笠原礼法ですが、明治維新後「武士のたしなみ」として社会的意義が喪失するにともない、技術論だけが婦女子教育に持ち込まれ、型ハメ式の堅苦しい作法教育として広まってしまいました。
先代宗家の小笠原忠統氏は、これを憂いて、礼法の本質を広く社会に知らしむべく、家中秘伝の封印を解いて、門弟の育成に取り組み始めたのが、いまの小笠原礼法宗家の活動につながっているそうです。
現在は、伝書の数々は、免許皆伝を受けた高次の門弟だけが原書を読むことが許されているとのこと。
小笠原敬承斎さんによれば、礼法は、礼儀=精神論と作法=技術論からなり、「こころ」と「かたち」を一体化されたものだそうです。
「こころ」の真髄は、「相手を思いやること」にあり、「かたち」はそれを具現化したものであって、「かたち」に囚われすぎることを強く戒めているようです。
小笠原敬承斎さんは、「礼法は臨機応変であることが重要だ」と言います。
「無躾は目に立たぬかは躾とて目にたつならばそれも無躾」
躾とは、あくまでも自然体でなされるもの。躾をことさらに際だたせてしまったとしたら、それが既に無躾になる。
なにやら、禅問答のような奥深さを感じます。
伝書に見る「礼法のこころ」として、敬承斎さんが紹介してくださったのが、下記の3箇条の教えです。
「人は大かた高きもいやしきも人のために辛苦をするならいななり」
礼儀は下の者が上の者に対する敬いの気持ちだけではない、上の者・下の者双方が互いに相手を敬い合う双方向のものである。
「貴人に対して礼儀するは、貴人に対して不礼なり」
相手を敬うあまりに、ことさらに礼を厚くすることが、周囲に気をつかわせる場合には、あえて、礼儀を省略することも、また礼儀である。
空気を読めということでしょうか。
「人はこころの中にたのしみを思うべきなり」
緊張した日々の中にも、こころ豊かに生きるための楽しみをみつけることもまた、たしなみのひとつである。
「武家のたしなみ」としてまとめられた言葉ではあっても、現代人にとって示唆のある教えではないでしょうか。
礼法の本質は「つつしみ」のこころだそうです。
月の満ち欠けの繰り返しの中に、限りなく続く生死の輪廻を見いだし、栄えるものの中に、衰退の哀れを感じ、滅びゆくものの中に、生命力の発露を発見しようとする「侘び・さび」のこころにも通じる、日本ならではの世界観がそこにあります。
登録

人気の夕学講演紹介
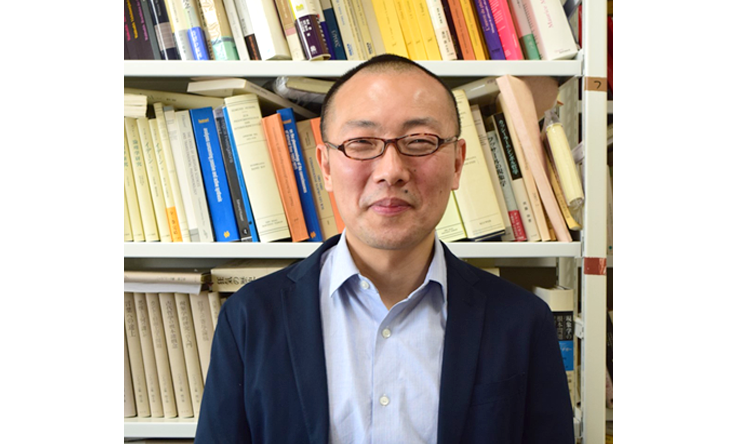
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
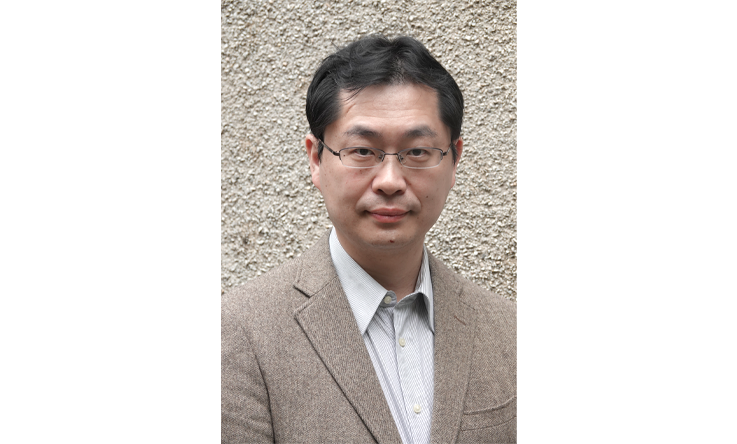
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




