夕学レポート
2012年12月20日
人生を引き受けるということ 樹木希林さん
 樹木希林さんは、5歳違いの実妹で、琵琶奏者の荒井姿水さんと供に登壇した。
樹木希林さんは、5歳違いの実妹で、琵琶奏者の荒井姿水さんと供に登壇した。
薩摩琵琶の音色に合わせて、お気に入りの「詩」を朗読することから、この日の講演は始まった。
「最上のわざ」(Hermann Heuvers)
http://home.interlink.or.jp/~suno/yoshi/poetry/p_thebestact.htm
最近公開の映画『ツナグ』の中で、樹木希林さんは、監督にお願いして、自らこの詩を紹介するシーンを入れたのだという。
この世の最上のわざとは何か。
それは、老いていく自分をありのままに受け入れて、従順に、静謐な心で過ごすことだ。
講演の演題「老いの重荷は神の賜物」はこの詩の一節に由来している。
樹木希林さんは、文学座の大先輩長岡輝子さんに教えてもらったこの詩を大切にしてきたという。
11月に夕学に登壇された南直哉師は言った。
人間は、その宿命として「存在することの不安」を抱えている。
人間は生まれてきた理由など知らない。なぜいま、ここで生きているのか、誰もわからない。「存在することの不安」を抱え続けて生きているのが人間である。
しかしながら、元気な時、若い時にはそれに気づかない。
病や老いを自覚すると、不安の重さにはじめて気づくものかもしれない。
樹木希林さんも、何度も病気を繰り返した。
間を置くことなく映画やテレビ・CMに出演し、強烈な存在感を発揮してきたので気づかなかったが、この10年程は病気の連続だったようだ。
肺炎を繰り返して三度入院、網膜剥離で左目を失明、乳がんで切除をしたが、全身に転移・再発を繰り返した。
その身体で、よくあれだけ映画やテレビに出続けられたのか、不思議に思うほどだ。
病や老いは、答えのない問いと向き合うことでもある。
名医や特効薬はあれども、人によっては合わないこと、効かないこともある。
老化防止の方法も数多あるけれど、不老でいられる人間はいない。
いずれも唯一絶対の解答がない問いを抱えて苦しまなければならない。
しかし、冒頭の詩に擬えて考えれば、それは、人間が人生の最後に取り組む「最上の仕事」なのかもしれない。
樹木希林さんの話には、最上の仕事に向き合うにあたっての気負いや重さのようなものが一切ない。ただただ、淡々として、他人事のようでさえある。苦労話を笑い話に変えてしまう。
何処にでも流れ行き、どんな色にも染まり、それでいてあらゆるものを洗い清め、時にすべてを流し去り、跡形だけを残して消えていく。そんな”水のような”人である。
希林さんは、老いていく身体も、病気で傷ついた身体も、女優としてはかけがえのない資産、使わない手はないと考える。
部分入れ歯の自分が、会話の最中に入れ歯を飛び出させるシーンがどこかで使えないかと狙っている。
乳がんで片方の乳房を切除した姿を、ヌードシーンで登場させられないかと真剣に考えている。
そんなことを、面白おかしく語ってしまう。
女優として、世の中に自分を晒してきたから、自然と自分を客観視することが出来るようになった。役者になってよかったと思う。
樹木希林さんは、そう語る。
これこそが「最上のわざ」であろう。
講演の最後で、文藝春秋新年特別号に寄せた、杉村晴子さんの紹介文を朗読された。
樹木希林さんが直接見聞した杉村さんのことばを中心に綴った思い出である。
樹木さんは、あたかも杉村春子さんを演じるかのように会話を再現する。それが驚くほど似ている。
長岡輝子さん(先述)、加藤治子さん、大空真弓さんなど、ゆかりの深い人々とのエピソードを語る時も、決まってその方を演じるようで、実に臨場感溢れている。
そのたびに、樹木希林さんが映画やテレビで演じてきた、さまざまなタイプの役柄が想起してくる。
かけがえのない人との出会いもまた、自分の血肉にしてきたに違いない。
来年のお正月も、富士フィルムの「お正月を撮そう!」シリーズの新バージョンがある。樹木さんが、綾小路さゆり役で登場する名物CMである。
「昔は、振り袖着ても顔の下に首があって、胸があったのに、今じゃ首の下がすぐ帯なんですよね」
最後まで会場を沸かせてくれながら、老いを受けいれ、演じ、生きている自分を淡々と語り切ってくれた。
登録

人気の夕学講演紹介

2025年7月2日(水)
18:30-20:30
音楽界の変革と未来:ヴァイオリニストが見る可能性
廣津留 すみれ
ヴァイオリニスト
音楽業界の変遷や舞台袖の裏話、これからの「好きなことを仕事にする」生き方についてお話しします。

人気の夕学講演紹介
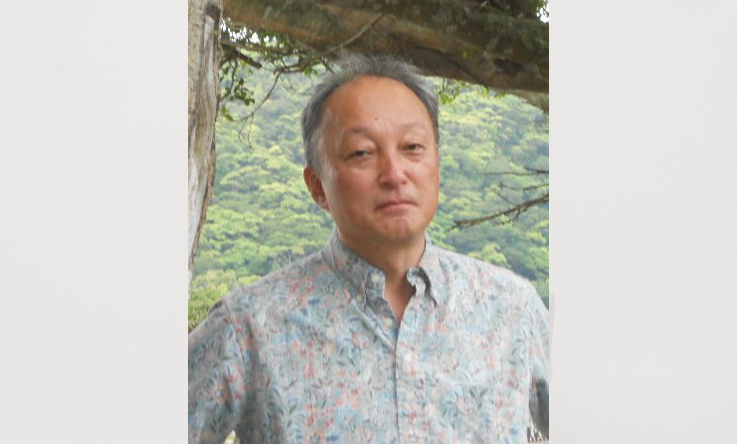
2025年7月10日(木)
18:30-20:30
家族と少子化の経済学
山口 慎太郎
京都大学大学院理学研究科 教授
科学的なデータと分析から浮かび上がる、これからの日本の家族と社会のありようについて、考えを深めていきましょう。

人気の夕学講演紹介
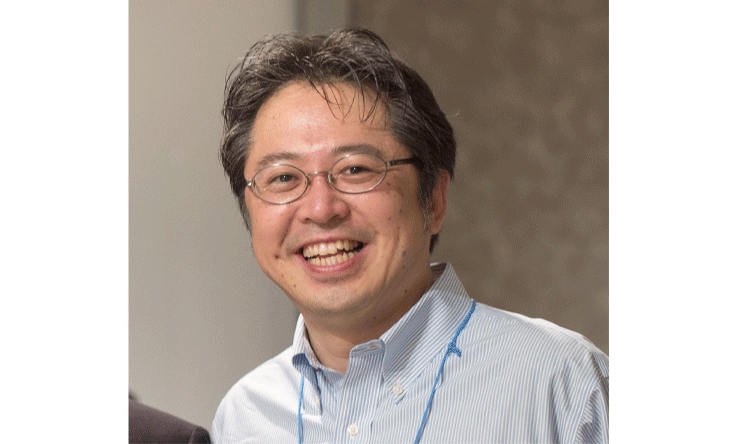
2025年7月18日(金)
18:30-20:30
残すに値する未来を考える
安宅 和人
慶應義塾大学環境情報学部 教授
LINEヤフー(株)シニアストラテジスト
都市集中型社会に対するオルタナティブ検討をこれまで7年半行ってきた活動から見えてきているfindings と意味合いについて議論します。
登録




