ピックアップレポート
2014年10月14日
岡田 正大「シナリオ分析と多様性で危機に備える」
「逆張り投資」を活用した信越化学
不確実性とは何か。フランク・ナイトによれば事象が発生する確率分布が不明な度合いを意味する。これは「ナイトの不確実性」と呼ばれる。一方、不確実性という言葉は確率分布が判明している「リスク」と同義で使われることも多い。
ヒュー・コートニーらによると、不確実性は4段階に分けられる。低い順から、(1)確実に見通せる未来、(2)複数のシナリオが想定される未来、(3)可能性の範囲が見える未来、(4)全く読めない未来―となる。(2)~(4)がナイトの不確実性やリスクの領域である。本章では、これら3段階をまとめて「不確実性」と定義する。
伝統的な戦略理論に沿えば、企業の業績を左右する要因は事業の外部環境と、企業が持つ資源や能力といえる。米企業463社の2810事業を対象にしたリチャード・ルメルトの研究(1991年発表)に基づいて推定すると、業績(総資産利益率)を変動させるのは業界固有の要因が1割、企業と事業の個別要因が4割、好不況の影響が1割だといえる。
残る4割の大半は不確実性だ。具体的には市場ニーズの思わぬ変化、法制度の急な変更、天変地異、エネルギー価格や為替相場の急変などだ。
こうした不確実性をうまく活用している好例が信越化学工業である。同社は世界中の顧客との間に張り巡らせた情報網をうまく活用し、原料や素材の市況変動を素早く予測。これを生かす形で競合他社が及び腰の不況期に逆張りの増産投資を実行、世界市場での占有率を高めてきた。
不確実性の時代に生きる現代の経営者は、事前に資源配分を最適化する伝統的な「事前意図的戦略」に加え、リアルタイムで不確実性に対処、積極的に活用する戦略の採用も求められている。
先制的破壊で世界標準をつくる
企業が不確実性に対応するには2つの大きな方向性がある。自社の意図的な行動で不確実性を解消する「能動的方法」と、複数の起こり得るシナリオに対して柔軟に対応する「受動的方法」である。今回は能動的方法の代表例である先制的破壊戦略を取り上げてみる。
戦略理論を研究するジェイ・バー二ーによると、先制的破壊戦略とは他社に先駆けて自社の事業を破壊する戦略である。
例として、米インテルとセコムを取り上げる。
インテルはパソコンの心臓部であるCPU(中央演算処理装置)の大手メーカーだが、自ら次世代のCPUを相次ぎ発売することで、それまでのCPUからの転換を強制的に促す手法を計画的に繰り返している。競合他社の新型CPUの攻勢にさらされた結果の窮余の策ではなく、インテルの高い技術力によって能動的に競争状況をコントロールする狙いである。
セコムの前身の日本警備保障は1964年の東京五輪の警備事業を受注した。この経験で得た強固な信用を基盤に、民間のオフィスビルなどを対象にした人的警備業でも警備員がパトロールする方式で絶大な競争力を獲得した。ところが同社は、この事業が拡大を続けていた66年、独自のセンサー技術を使った機械による警備に転換した。
警備員の巡回方式は当時の同社の”ドル箱”ビジネスモデルであり、これをいきなり新規の方式に変更する決断にはほかの役員や顧客が反対した。ところが、創業者の飯田亮氏は規模の経済性を発揮できる機械による警備の成功を確信。結果的に機械方式は成功して他社にも広がった。技術を先行して蓄積した同社は警備業界をリードし、市場全体を拡大させた。このように先制的破壊戦略は、一般にその業界で最高水準の技術を持つ企業が実行し得る。自社の製品やサービスを業界標準に置き換えることで、技術と需要の不確実性を能動的にコントロールするのである。
偶発的成功に端を発する「創発戦略」
企業が不確実性に対応する受動的方法の一つとして「創発戦略」を取り上げる。提唱者のヘンリー・ミンツバーグは「戦略とは偶然と熟慮両方の産物である」と指摘した。
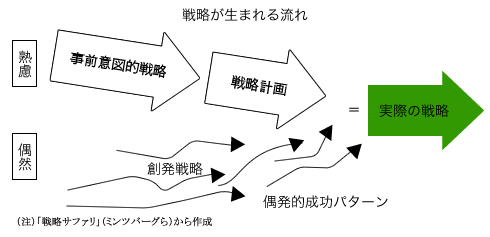
「偶然」とは、企業の戦略策定者が意図しない偶発的な成功を意味している。「熟慮」とは伝統的な戦略理論に基づいて、企業内の資源配分を事前に考慮して最適化することである。
そして『創発』とは先に述べた『偶然』に呼応するものであり、複雑系理論における創発現象を背景に、組織の中枢が意図を持たなくても何らかの秩序が生まれるような状態を表している。
ミンツバーグによると、組織の中枢にいる者が資源配分を最適化する従来の戦略プロセスは、事前に処方箋を用意する戦略プログラミングといえる。ところが現実にはこのプログラム通りに事は進まず、現場での試行錯誤や偶発的事象により成功に到達することもある。
世界規模でホテルチェーンを展開する米マリオット・インターナショナルは1930年代、ワシントン郊外の空港に近い「ホットショップ」という飲食店だった。創業者はある時、食事どきになると乗客が食べ物を買って空港に向かう事実に気づいた。そこで機内で食事を提供するビジネスが成り立つと考え、航空機向けのケータリング(仕出し)事業に進出した。これを足がかりに、ホテル業界でも成功を収めた。
事前の意図と異なる偶発的成功を例外として見過ごさず、価値を柔軟に認めて戦略を修正した結果、まったく新しい戦略が形成されることがある。これが「創発戦略」だ。小さな偶発的成功を事業上の大きな成果に導くことを可能にする。
オプション的発想で機会損失削減
リアルオプションとは、金融オプションの考え方を参考に、実物資産への投資意思決定を行うダイナミックプログラミングの手法である。不確実性が比較的大きな製薬、不動産、ITなど様々な業界で活用できる。この手法では、初期少額投資の実行と柔軟性の確保が鍵となる。段階的に意思を決定、その時々で不確実性を考えて事業の継続、修正、撤退を決める。
レノ・トゥリジオリスはリアルオプションを(1)延期、(2)拡張、(3)縮小、(4)切り替え、(5)一時休止、(6)廃棄、(7)複合―の7タイプに分類した。第一節で紹介した信越化学工業の「逆張り投資」は(2)の拡張オプションを内包している。
図はベンチャー企業を買収する案の是非を廃棄オプションとして分析するシナリオツリーだ。まず買収金額として60億円を支払う(図中にマイナス60億円と表記)。買収後1年目の正味現金収支(利益)は50%の確率で高い(60億円)か低い(0円)かに分かれ、2年目も等確率で図のように分布すると見込まれるとしよう。
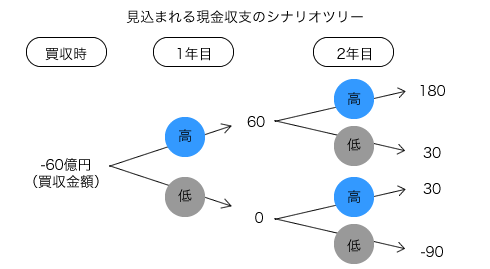
伝統的なディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法では、図のシナリオがすべて生じるという前提で、買収前の時点で、この案件の価値を算出する。仮に必要とされる収益率が年15%ならば買収案の価値はマイナスとなり、この提案は却下されるはずだ。
一方、リアルオプションの発想では1年目末の時点で需要が低かったと判明した時点で当該事業自体を廃棄すると考える。すると2年目に正味利益が50%の確率で30億円かマイナス90億円に落ち込むという、期待値がマイナスのシナリオは回避できるので、買収案は実行される。
このように、事業の価値変動などを推定できる場合はリアルオプションが使える。不確実性の大きな事業シナリオに柔軟性を与え、従来は却下された提案を採択し、機会損失を減らすことができる。ただし、伝統的日本企業に特有の限界は、組織の慣性や責任回避の心理から、このケースの『廃棄』にみるような経営資源の組み換えが迅速に実行できないことにある。この問題の背景には責任回避の指向性が強い組織の価値観や企業統治の不十分さなど、解決すべき重要な課題が潜んでいることも忘れてはならない。
「みんなの意見」は案外正しい
企業戦略における重要なテーマの一つは、不確実性が大きな状態での予測能力である。ここでの巧拙は企業の業績を大きく左右する。いま話題のビッグデータ分析も、推測能力を高める手法だといえるだろう。実は前節で紹介した『リアルオプション』には、日本企業特有の問題以外にも深刻な限界がある。その代表例が将来予測の難しさである。
リアルオプションによる事業シナリオの分析に用いる将来のキャッシュフロー(現金収支)や事象の発生確率の精度が低ければ、いくら手法を正確に用いても結果は信用できない。いかなる事業計画にも予測は大きな要素として含まれるが、それが恣意的にゆがめられることも多い。そうなるとリアルオプションによる合理的な意思決定は深刻な打撃を受ける。
この問題を解消する切り札として注目されるのが「予測市場」だ。これは「集合知」の活用を背景とする。要するに「みんなの意見」は案外と正しいということである。
「ウィズダム・オブ・クラウズ(群衆の叡智=えいち)」の著者ジェームズ・スロウィッキーによると、少数の専門家による予測よりも、その事象に関わる多様で多数の個人が参加する予測の方が高精度だ。米アイオワ大学が米大統領選挙の結果を予測するため開発してきた手法として知られる。株式市場の売買メカニズムを使い、予測対象の事象に関わる多数の市場参加者の判断を一つの予測値へと集約する。
この手法を用いて、かつて米映画界のアカデミー賞8部門の大半を的中させた会社もあった。
米マイクロソフトは社内に多数の社員が参加する予測市場を設け、同社の大規模開発プロジェクトの完了時期を推定しているといわれる。
山口浩駒澤大学教授によれば、予測市場に参加する社員の当事者意識は強まり、仕事への意欲も高まることが多い。社員が積極的に情報を収集することで予測精度が向上することもある。
新興国でビジネス生態系
新興国市場では慣れ親しんだ先進国市場よりも不確実性が大きな場合が多い。こうした外部環境の不確実性への耐性をいかに高めるべきか。有効な手段の一つは、社外の様々な企業や団体とネットワークを形成する戦略だ。このネットワークをビジネス生態系と呼ぶ。
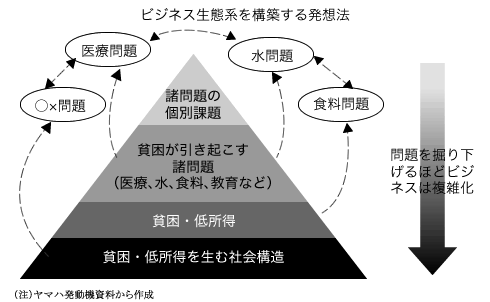
すべてを自社機能でまかなうのではなく、様々な能力を持つ企業や団体と連携して不確実性を解消する。こうした戦略的な提携の事例はこれまでにも無数に存在するが、昨今の特徴はそこで国際機関、非政府組織(NGO)、NPOとの関係構築も目立っている点だ。
私が調査したサブサハラ(サハラ砂漠以南)アフリカの市場では、様々な企業や団体が加わるビジネス生態系が1社の資源だけでは対応できない仕事を補完することで成功している事業がある。
例えばヤマハ発動機は西アフリカのセネガルにおいて、従来のバケツによる給水が農業生産性の上昇を妨げている事実に着目。同社の灌漑用ポンプを拡販するだけでは一時的な解決にしかならないと判断し、先進的な灌漑技術の普及を視野に農業生産性の上昇を抑えている真の要因を探った。図では、その際の発想法を示した。
結果として、すべての作業を同社が単独で実施するのではなく、金融はベルギーのNGOのセネガル支部、灌漑手法は超節水型灌漑技術を持つネタフィムジャパン(東京・中央)、宣伝・広報は現地の自治体と連携し、ヤマハ発動機が中核となるビジネス生態系を構築した。
この戦略は、経路依存性(その企業独自の時間的地理的経緯)と社会的複雑性(独自の人間関係)から競合他社の模倣が容易でないために排他性があり、実は参入障壁としても有効に機能する。
社外と連携し課題を解決
ベンチャー企業など社外パートナーと連携して研究開発を進めるオープンイノベーションの手法は、ヘンリー・チェスブローの著作「オープンイノベーション」で広く知られるようになった。
例えば、高度なインターネットの検索エンジンシステムも、新興企業の新製品に駆逐される可能性が常にある。しかし、それがいつどのように起きるかを予測するのは難しい。自社内外で生じる技術革新にも不確実性がある。
また自社技術の製品化を異業種の他社に委ねる方がよりよい結果につながるケースもあるはずだ。
こうした問題意識もオープンイノベーションにつながる。技術の入り口も出口も、開かれた市場空間で最適な資源の組み合わせを選択できれば、結果として生み出される経済的価値は拡大するという考え方である。ここでは「オープンイノベーション」に掲載された両開きのじょうごのような図に加筆して掲載した。
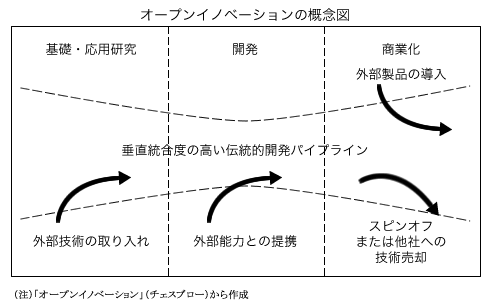
この手法を代表する事例が米イーライリリー社である。自社の研究開発課題の解決を一般公募するスキームを構築したところ、効率よく回答が得られたため他社も利用できる開放型のプラットフォームとして事業化した。それが米イノセンティブ社である。同社は顧客企業の研究開発テーマの解決策を一般から公募、数万ドル以下の報奨金で買い取る仲介市場を運営している。
回答するのは企業の研究者、主婦、学生など多様な個人だ。開かれた市場空間で不確実性を解消する戦略で、インターネット経由で企業が個人に仕事を委託するクラウドソーシングの原型といえよう。
組織の内部に多様性を備える
多様で不確実な環境の中で企業はどうやって存続し、発展するのか。生物や機械の制御理論とコンピューターを総合した科学であるサイバネティクスが専門のウィリアム・アシュビーや高木晴夫慶応義塾大教授は、そのために外部環境を上回る多様性を組織内部に備える必要があるという。
組織内部の多様性を高めるには、多様で強い個の力を持つ人材が不可欠だと考えられる。ところが、これは心地よい同質性の否定につながり、伝統的な秩序を持つ組織ではなかなか受け入れられない。結果として、多様性を増し続ける外部環境に適合することはますます難しくなってしまう。
個の力を強調すると「組織の力こそが日本企業の強みだ」と主張する向きもある。もちろん組織力は大切だ。だが個人の能力を高めずに団結だけを強調した結果、単に責任をとれない個人の集合体に陥る危険は避けるべきだろう。リスクを請け負う能力のある多様な個人を育成することは、組織が不確実性に挑む重要な前提になるはずだ。
能力の多様性を高める方法は採用や配置など様々だ。優秀な社員をグローバルな起業家ネットワークに預けて独力で事業構想を追求させ、そこで得た突破力をもとの会社に戻ってから発揮させる手法も有効である。
例えば2005年にロンドンでジョナサン・ロビンソンと3人の仲間によって設けられた起業家の交流組織「ザ・ハブ」の拠点は世界の約40都市に広がり、東京では12年に開かれた。さらに600都市で開設準備中だ。
ここまで8つの節にわたり、企業が自社に利するため、いかに不確実性に取り組むべきかを述べてきた。共通するのは、企業が自社の内部の経営資源だけにこだわらず、常識を超えて社内外の様々な能力や知見を持つ個人や組織と結びつく柔軟で機動的な姿勢である。これが不確実性を解消する基本だといえる。
日本経済新聞出版社『仕事に役立つ経営学』序章より著者と出版社の許可を得て転載。無断転載を禁ずる。
- 岡田 正大(おかだ・まさひろ)
-

- 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 ビジネス・スクール教授
- 昭和60年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。(株)本田技研工業を経て、平成5年慶應義塾大学経営学修士(MBA)。Arthur D. Little(Japan)を経て、米国シリコンバレーのMuse Associatesに参画。平成11年オハイオ州立大学経営学Ph.D.を取得。同年、慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師、平成14年助教授・准教授を経て平成25年10月より現職。
- 担当プログラム
登録

オススメ! 秋のagora講座

2024年12月7日(土)開講・全6回
小堀宗実家元に学ぶ
【綺麗さび、茶の湯と日本のこころ】
遠州流茶道13代家元とともに、総合芸術としての茶の湯、日本文化の美の魅力を心と身体で味わいます。

オススメ! 秋のagora講座

2024年11月18日(月)開講・全6回
古賀史健さんと考える【自分の海に潜る日記ワークショップ】
日記という自己理解ツールを入口に、日常を切り取る観察力、自分らしい文章表現力と継続力を鍛えます。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録





