今月の1冊
2015年11月10日
『世界のエリートが学んできた 「自分で考える力」の授業』
最近、わが子たちと会話をしていて不安を感じている。
日常生活のたわいない会話なのだが、子供たちが反射で返してくる。小さい時はめちゃくちゃながらもそれなりに思考している様子がうかがえたものの、成長するにしたがってやりとりが減ってきた。人に判断を任せすぎてはいないか?おおらかに育てる方針の私なのだがさすがに危機感を抱く。
たとえば何か頼みごとをする。子供たちは、「むぅ~りぃ~(無理)♪サファリパ~ク♪」や、妖怪キャラクタさながら両手を開きながら顔を突出し「むぅ~りぃ~(無理)♪」で返してくる。この手はまだかわいいが、「無理」と一言だけ返ってくることもあり、瞬間的に頭に上った血を抑えるのに苦労する。冷静さを装って「どうして?」「お願いしたいのだけど・・・」と言ってみる。それでも返ってくるのは「無理」の一言。
たとえば毎朝の光景。子供たちから「今日は暑い?寒い?」と必ず質問がでる。1分たりとも無駄にできない時間だ、台所のラジオから聞こえた本日の最高気温を思い出しながら、私は「暑い」とだけ答える。すると子供たちは半袖を来て登校する。
ある朝、残暑の残る9月だったが、私は「寒い!」と答えてみた。すると・・長袖を着ていた。太陽がすでにぎらぎらと照りつけているというのに。
そんなころ出会ったのが、『「自分で考える力」の授業』。
本書は、クリティカルシンキングをもとに日本の学校が教えていない「考え抜く力」を、欧米の学校の教え方をヒントにビジネスパーソン向けに教示する。
クリティカルシンキングについて書かれた書籍は良書が多数出版されているが、私は以下の3点において本書に魅力を感じ、未来のビジネスパーソンを、今、育てている皆さんと共有したいと思う。
1つ目は、著書狩野みき氏の実体験に基づくアプローチ。
大学で英語教育に20年以上携わっていらっしゃる狩野氏が、このアプローチを開発したのは、日本人はかなりの英語力を持っているにもかかわらず、「話すという行為」において英米人とは大きな差があると感じたからだという。その決定的な違いは「意見の濃厚さ」にあるらしい。日本人の思考パターンと英米人のそれとの違いを意識しながら、日本の学校では教えてくれなかった「意見の作り方」の指導法を組み立てていること。
グローバルな社会で今以上に活躍するであろう、これからの子供たちにはこのアプローチは有効ではないかと考える。
2つ目は、ケース紹介が子供の授業風景であること。
本書はビジネスパーソン向けに書かれた書籍ではあるが、各コーナーの最初には小学生を対象にした「授業風景」があり、日常生活でのイメージがしやすい点にある。
子ども「今日は、僕の大好きな車のオモチャを持ってきたので、それについて話をします。かっこういいでしょう?これはスポーツカーで、ボクの歳の誕生日にパパが買ってくれたんだ、いつも一緒に遊んでいるんだよ。お兄ちゃんが貸してって言うけど、絶対に貸さないんだ。だってボクの大事な、宝物だもん」
先生「その車はパパに頼んで買ってもらったの?」
子ども「そうだよ!ずっとこの車が欲しかったの」
先生「どうしてその車が大好きなの?」
子ども「え?! どうしてって・・・えーっと・・・どうしてかな・・・わかんない・・」
いかかがですか?みなさん、ここまで子供と会話を深めていますか。
我が家の日常は・・・
3人の子供たちは我先にと一斉に今日あった出来事を話し始める。1人目の子供が話し終わった瞬間に、次の子供が話を始める。「そうだったんだね・・・よかったね。」とだけ返して、次の子供の話を聞く。そんなことをしているうちに、夕食だ、宿題だ、入浴だ・・・と牧羊犬のように子供たちを追い立て、最後は子供たちとともに布団に倒れこむ。そんな毎日が脳裏に浮かぶ。
この事例を目にして、日々の何気ない会話も、投げかけ方一つで、子どもはもう一段深く考える機会を与えることができると気づかされた。
そして最後は、「自分が大切に、大事にしていることを知ること」は「自分の意見」を考えるにあたって重要である、と述べている点にある。
ひとりよがりではない、健全な「自分だけの答え」や「意見」は、じっくりと主体的に考えるプロセスを経たうえで、さらにその人にとって「大事なこと」が核にある意見には、覚悟があると述べている。
自分が大切にしていること、大事にしていることをどうやって知るのか、それは、「ん?」という気持ちに気付いて、その理由を探ってみることだという。
「何かおかしい」「何かいいなぁ」「何か気になる」という気持ちは、「多くの場合、その人にとって大事なことである」。言語化していない、もやもやした気持ちの実態を探ることで自分を知ることができる。
私たちは日々の生活の中で多くの思考を繰り返し、その習慣化した思考は、何もしなければ変わらない。これまでの習慣を少し変えてみたら・・・子供たちの何気ない一言を、私たち大人が少しだけ掘り下げて問いかけてみれば、彼らの思考の枠を広げることができるのではないか。
また、産業革命で人間の労働が機械に代わったように、いつの日か人工知能が人間の思考の一部を代替・凌駕するようになるだろう。そんなとき子供たちが、人間だからできることは何か、本当に人がすべきことは何か、考えてほしいと思う。
本著はそんな希望を私に持たせてくれる一冊であった。
著者のアメリカ人の友人は、幼稚園の頃、先生に「なぜそのオモチャが好きなの?」と尋ねられ、答えられずにうろたえたそうである。しかし学校や社会で自分の意見を求められ、伝えてきたからこそ、今、自分の意見としてしっかり伝えることができるようになった。
今朝もまた「パーカーいる?」と子供が質問してきた。
「気温は18度だって。外に出て寒いかどうか確かめておいで」と言ってみた。返ってくる返事は同じであっても、あきらめずに、明日もあさっても「どうして?」と問いかけ続けてみよう。
(前田祐子)
登録

人気の夕学講演紹介
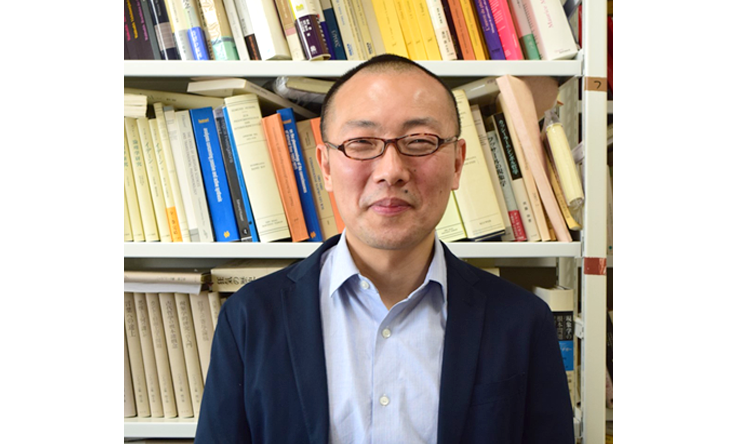
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
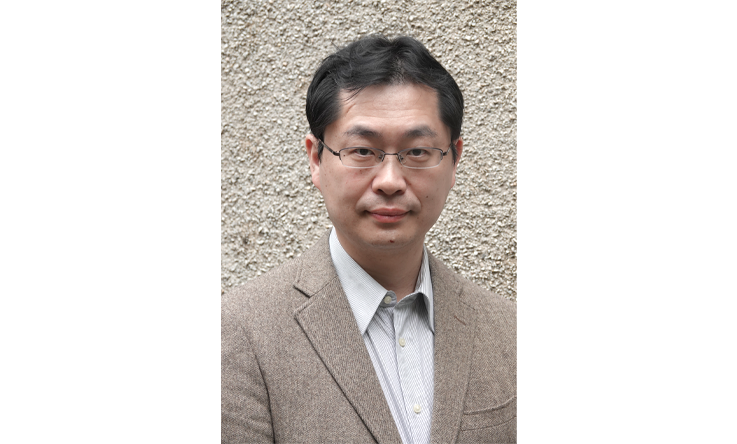
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録





