2010年06月08日
動きながら道を探した人 正岡子規
【人気ブロガー マサオカ・ノボル氏が死去】
詩歌・小説・随筆など多彩な創作活動を行う一方で、文学・映画・演劇・時事問題まで幅広い領域で評論活動を行ってきたマサオカノボル氏が、9月17日未明、脊椎カリエスのため、自宅で亡くなった。享年35才。
権威や既成価値に対する挑戦的な態度で知られ、評論では、各分野の大御所・大家を厳しく指弾する論陣を張り、その都度大きな話題になった。
15歳での世界一周旅行に始まり、数度の冒険旅行や紛争地帯への取材旅行を敢行し、ウサマ・ビンラディンや金正日との会見にも成功した。
ここ数年は持病が悪化し、自宅療養が続いていたが、自らの病状や生活の様子を綴ったブログ「仰向け人間の独り言」を毎日更新し、赤裸々に感情を吐露することで、多くの人々の共感を呼んだ。
正岡子規が、もし現代に生きていたとしたら、きっと彼の死は、このように報じられたのではないか。
子規は、この世に生まれ出るのが百年早過ぎた。
彼が生涯を通して見せた「自由意志」「行動力」「好奇心」「反骨精神」「表現欲求」は、明治という時代の枠からは、大きくはみだしている。
その才能は、現代でこそ活きる。きっと日本を代表する、いや世界と日本の位相を描き出すようなマルチ文化人になっていたに違いない。
動きながら道を探した人
子規をひと言で言い表すとしたら、こう表現したい。
彼は、静かな思索の中で自己の進むべき道を見出した人ではない。内側から沸き出でる衝動を抑えることなく、いつも、まずもって行動を起こした人間である。
15歳での上京、文学への没入、東京帝大中退、日清戦争への従軍、俳論・歌論への傾斜etc
彼は考えてから動くのではなく、考えた時にはすでに身体が動いていた。
道は選ぶものではなく、決められたものであった時代にあって、彼ほど好奇心に忠実な態度で道を選び取った人は珍しいのではないか。
時に、その態度は既成の権威に対する激しい挑戦として発露することもあった。
「貫之は下手な歌よみにて、古今集はくだらぬ集にて有之候。その貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬこと...」
短歌論『再び歌よみに与ふる書』は、激しい挑発の言葉からはじまる。紀貫之、『古今和歌集』という平安文化を代表する権威に対して、試合開始からいきなりビーンボール投げつけるようなものだ。その心意気やよし。
彼はいつも、動きながら道を探した。周囲の人々や風景、出来事とガシガシとぶつかり合いながら、身体にできた痣の痛みと会話して、進むべき道を見つけた。だからこそ、彼の周りには、いつも人が集った。
秋山真之、夏目漱石、高浜虚子、陸 羯南...。 友は彼を愛し、弟子は彼を慕い、師は彼を慈しんだ。
子規がいなければ、漱石は小説を書くことはなかった。
子規がいなければ、虚子・河東碧梧桐は埋もれていた。
子規がいなければ、司馬遼太郎は『坂の上の雲』を書かなかった。
きっとそうに違いない。
彼が、あと20年長く生きたら、親友の漱石の成功に刺激されて、再び小説に挑戦したかもしれない。50年長生きしたら映画を作っただろう。海外にもどんどん出かけたのではないか。現代に生きていれば、アフガニスタンの山中に分け入ったり、厳冬の豆満江を渡ったのではないかという妄想を沸き立たせてくれる。
表現者として生き、表現者として死ぬ
「僕ノ今日ノ生命は『病床六尺』にアルノデス。毎朝寝起ニハ死ヌルホド苦シイノデス。ソノ中デ、新聞をアケテ『病床六尺』を見ルト僅ニ蘇ルノデス...」
子規は、死の5カ月前から二日前まで、新聞「日本人」紙上に、随筆『病床六尺』を書き続けた。(すでに筆を取る力はなく、弟子の高浜虚子が口述筆記をした。)
新聞社が、子規の身体を慮って休載日を作ったことに対して、子規は、こう訴えて連載を懇願している。
漱石は若い頃の子規をして、「年がら年中、何かを書き続けていた」と評しているが、書くことへの異様なまでの執念は、死ぬまで衰えることはなかった。
子規が病んだ脊椎カリエスとは、結核菌が脊髄を冒し、身体中に穴があく。末期の病状は、筆舌に尽くしがたい悲惨なものであったという。死臭が漂う四畳半で、モルヒネが効く僅かな時間を使って、子規は歌を詠み、スケッチを描き、随筆を書いた。
書くこと、表現することで、破綻寸前の精神バランスを取っていたのかもしれない。
それがもっとも強烈に表出しているのが『仰臥漫録』である。
他の作品と違い、公開を前提としない私的メモとして、書きなぐるように記録されたこの書から、子規の身体に巣くった、凄まじいまでの餓鬼が垣間見える。
消える寸前の生命に対する最後の執着を、食欲に凝縮させた哀れな姿が、淡々と続く記述を通して描かれている。読むものに、生きることの醜さを、これでもかと突きつけてくる。
明治三十四年九月某日に記された一日の食事内容を紹介すると、
朝は「ヌク飯三椀、佃煮、ナラ漬」、
昼食は「粥三椀、焼き鴨三羽、キャベージ、ナラ漬、梨一個、葡萄」、
間食は「牛乳ココア入り、菓子パン10個ほど、塩煎餅」
夕飯は「与平寿し二ツ三ツ、ヌク椀二椀、マグロのサシミ、煮茄子、ナラ漬、葡萄ひと房」
他日にも、当時高級品であったココアや菓子パン、マグロ、メロンなどを大量に食していることがわかる。
すでに、この頃の子規は、床から起き上がることさえ出来なかった。食べ過ぎで腹をこわし、胃腸薬を飲みながら、それでも食べる。
自殺未遂の告白もある。
看病する母、妹がたまたま外出してしまい、わずかな時間ひとりになった子規は、にわかに寂寥感に襲われ、衝動的に手元にあった小刀に手を伸ばす。
「たまらんたまらんどうしやうどうしやう」
かろうじて思いとどまった後、モルヒネで精神を落ち着けたうえで、自分がのど笛を掻き切ろうとした小刀をスケッチする。
子規は、句や歌においては、とりわけ「写生」にこだわった。
彼は、小刀を写生することで、自分を支配した死の恐怖と折り合いをつけようとした。
痛みにのたうちまわり、泣き叫び、家人に怒鳴り散らし、腐臭を体中から発しながらも、なお生きたいと願う地獄道を、隠すことなく書き綴る子規。
いや、書かなければとうの昔に狂っていたかもしれない。
書くこと、表現することは、子規にとって、呼吸や排泄と同じようなものであった。
彼の表現欲求を発現する場は、ネットこそがふさわしい。もし、現代に生きていたならば、きっと毎日長文のブログを更新しただろう。Twitterにも真っ先に飛びついたはずだ。
ひょっとしたら、you tubeで病状の様子を公開する位のことはやったかもしれない。
正岡子規は、表現者として生き、表現者として死んでいった。
最後に、子規の人間像を最もよくあらわしている歌を紹介して、長くなり過ぎた拙文を終わりにしたい。
この歌を詠んだ頃、子規はすでに立ち上がることさえ難儀になっていた。
足たたば不尽の高嶺のいただきをいかづちなして踏み鳴らさましを
足たたば二荒のおくの水海にひとり隠れて月を見ましを
足たたば北インヂアのヒマラヤのエヴェレストなる雪くはましを
足たたば蝦夷の栗原くぬぎ原アイノが友と熊殺さましを
足たたば新高山の山もとにいほり結びてバナナ植ゑましを
足たたば大和山城うちめぐり須磨の浦わに昼寝せましを
足たたば黄河の水をかち渉り崋山の蓮の花剪らましを
子規は、妄想の中でも「動きながら道を探す人」であった。
参考文献
『墨汁一滴』 正岡子規(岩波文庫・改版)
『病牀六尺』 正岡子規(岩波文庫・改版)
『仰臥満録』 正岡子規(岩波文庫・改版)
『回想 子規・漱石』 高浜虚子(岩波文庫)
『ひとびとの跫音』 司馬遼太郎(中央公論新社、中公文庫)
『坂の上の雲』 司馬遼太郎(文春文庫・新装版)
(城取一成)
登録

人気の夕学講演紹介
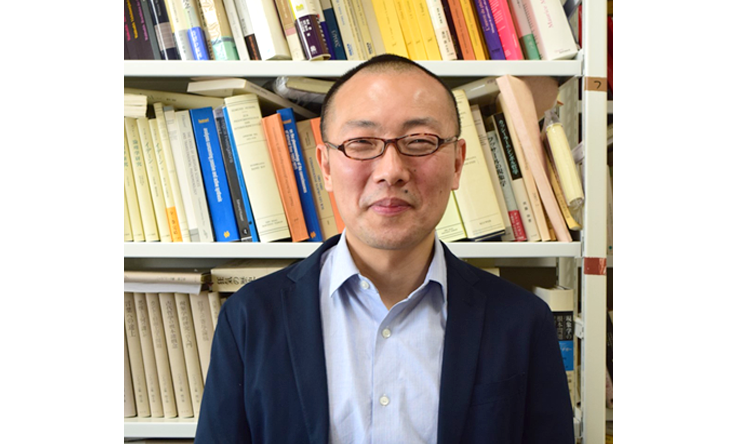
2024年7月19日(金)18:30-20:30
不易流行の経営学を目指して
~稲盛経営哲学を出発点として~
劉 慶紅
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
日本経営倫理学会常任理事
稲盛経営哲学に学びながら、人間性を尊重し、利潤追求と社会貢献の統合をめざす経営学理論を構築する、新論が真論となり、不易流行の経営学として結実することを目指して。

人気の夕学講演紹介
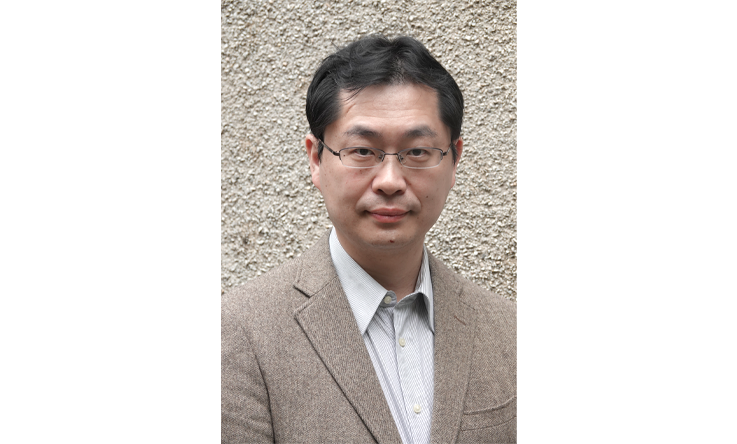
2024年7月23日(火)18:30-20:30
『VIVANT』とテレビ局社員
福澤 克雄
(株)TBSテレビ コンテンツ制作局ドラマ制作部、演出家・映画監督
私にとっての道は、TBSにありました。『VIVANT』は、同じような夢を持つ若者たちの道標になってほしい、そんな思いも込めてチャレンジした作品です。日本のドラマ界、映画界を目指す皆様、夢はあるけど方法がわからない皆様の一助になればと願っております。


いつでも
どこでも
何度でも
お申し込みから7日間無料
夕学講演会のアーカイブ映像を中心としたウェブ学習サービスです。全コンテンツがオンデマンドで視聴可能です。
登録




